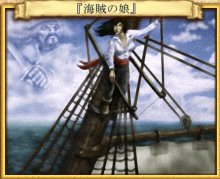



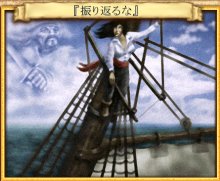

海賊の娘
| 1.海賊の娘 | 2.ブラディーコープ | 3.帰らずの海峡 |
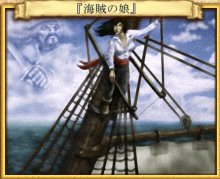 |
 |
 |
| 4.乙女の入り江 | 5.振り返るな | 6.ラストナレーション |
 |
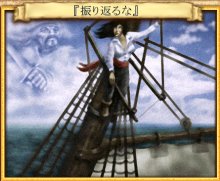 |
 |
−−海賊の娘−−
| 詳細 | |
| 勝利条件: | フリジンストンとヤナズレーを攻略する |
| 敗北条件: | タウニー・バルフォアまたはピート・ガーリーを失う |
| マップの難易度: | 「上級」ゲーム |
| 持ち越し: | タウリー・バルフォアとピート・ガーリー、および二人の呪文、技能、経験は、<<不壊の盾>>と一緒にすべて次のマップに引き継がれる。自軍の勇者の最大レベルは 12。 |
二人の水夫が親父の大きな死体を甲板から突き出した渡し板の端まで運んだ。死体を包んでいるのは切り取られた帆の一部だ。親父が食事代を払うのによく使っていた金メッキした鉛の硬貨を詰めた袋が、重しとして縛りつけられている。
全員の目があたしに向けられた。娘であり新しい船長でもあるあたしが、何か言うのを待っているのだ。だが、商売敵の刃によって命を落とさなかったら、今ごろはあたしが親父を殺していただろう。そんな女に何を言えというのだ?
「この肉の袋はかつてブラック・バルフォアと呼ばれていた」乗組員全員に聞こえるように、あたしは大声をはりあげた。「ブラック・バルフォアはあらゆる者をあざむき、打ち負かし、殺してきた」
全員が歓声を上げた。
酒瓶を手にしてあたしは渡し板に足を踏み出した。足の下で板がギシギシときしむ。乗っている人間が多すぎるせいで、今にも重みに耐えかねて折れそうだ。だが、あたしは板がきしむ不吉な音をあえて無視した。口を使ってコルク栓を抜き、中身をろくでなしの父親の死体にかける。中身があらかたなくなると、あたしはコルク栓をはき捨て、残りを一気に飲み干した。
「あばよ!」そう言ってあたしは水夫たちにうなづきかけた。
水夫たちがブラック・バルフォアの遺体を水中に投げ落とすのと同時に、あたしは酒瓶を投げ捨てた。じつを言うと、今朝、葬式の準備の最中に、重しを死体に縛りつけているロープにこっそり切り目を入れておいたのだ。二日もあれば、海が死体をきれいさっぱり掃除してくれるだろう。ブラック・バルフォアが<黄金海>の底にいられるのはほんの少しの間だけ。重しがなくなった死体は水面に浮かび上がり、幸運なサメたちのご馳走になるという寸法だ。
その光景を思い浮かべ、あたしは唇の端をゆがめた。
「お似合いの末路さ」誰にも聞こえないような小声であたしは言った。
甲板を踏んだ瞬間、あたしの腹めがけて剣の切っ先が繰り出された。あたしは眉一つ動かさなかった。女が船長になることをこころよく思わない者も少しはいるだろうと予想していたからだ。副長のゴリー・ゴーディーはさしずめその筆頭だ。あたしはゴーディーが尻尾を出すのを待っていたのだ。いざというときに備えて、あたしが着ている白いブラウスのダブダブの袖の中には二本の短剣がしのばせてある。だが、この葬式ではあえて丸腰にみせかけていた。ゴーリー・ゴーディーのような臆病者には、さぞかし格好の獲物に見えたことだろう。
あたしはサイドステップでゴーディーの剣をかわした。だが、スピードに乗った一撃を完全にかわすことはできず、臍の上を少し斬られてしまった。あたしは後ろに跳んでゴーディーの間合いから逃れた。周囲では、あたしたち二人を取り囲むように、乗組員たちが円陣を組んでいる。あたしは歯を食いしばって痛みに耐えた。
「ずいぶんとゆっくりだったじゃない」短剣はまだ抜かない。ゴーディーを油断させなければ。男ってのは、自分が有利だと思うと隙だらけになるものだ。
「ご遺体が海の底に沈んじまう前に、親父さんにそれなりの敬意ってやつを見せたくてな」
「笑えるね。親父はあんたにこれっぽっちの敬意も払っちゃいなかったよ。いつだってあんたのことをボンクラ呼ばわりしてたものさ。だから副長にしたんだよ。あんたみたいなおバカには、反乱なんか起こせやしないってタカをくくってね!」
「ベラベラとよく喋る娘だ」
さらに三回、ゴーディーが突きを入れてきたが、あたしはそれをことごとくかわした。
「丸腰の女に剣を持ち出すとはね。卑怯なんじゃない?せめてあたしに短剣をおよこしよ」息を整えるために動きがとまった瞬間を見計らって、あたしはゴーディーに言った。
「おことわりだ!そもそもお前なんて女じゃねえ!」
「あら、そう」そう言ってあたしは袖に手を入れた。「じゃあ、自分のを使うことにするよ」
一瞬、ゴーディーはキョトンとした。ようやく、思っていたほどあたしが無力ではないことを悟ったときには、すでに手遅れだった。あたしはゴーディーの動きが止まった瞬間を逃さず、一本目の短剣を投げつけた。短剣はゴーディーの右の腿に、柄まで深々と突き刺さった。こうなってしまったらゴーディーの剣は怖くない。片足しかまともに動かない状態であたしを追い詰めることは不可能だ。あたしはゴーディーの周囲を軽快なステップで動き回り、あざけりの言葉を投げつけ、何度か短剣で斬りつけた。やがてそれにも飽きると、あたしは素早くゴーディーの背後に回りこみ、振り向く時間さえ与えずにとどめを刺した。
あたしは血に染まった短剣でゴーディーの死体を指しながら言った。「海に投げ込め。それから誰か、あたしの船についたこいつの血を拭いておきな」
昨日、あたしは<暴風海峡>に向かうことを船員たちに宣言した。副長を始末して以来、操船はあたし自身の手で行っている。親父にはできなかったことだ。
今のところ船員たちは、タウニー・バルフォアがどんな船長になるか、あれこれ想像している段階だろう。あたしがなにをしようとしているのか、いぶかしんでいる者もいるはずだ。ふむ、あたしは連中をどこへ連れて行こうとしているのだろう?
まあ、悩むのは船員たちに任せておこう。連中があれこれ考えているうちは安全だ。混乱している男たちは、滅多に反乱なんて企まないものだ。
ノックの音が物思いにふけっていたあたしをドキっとさせた。
「お入り!」
若い水夫が二人、部屋に入ってきた。二人とも自分たちがなぜあたしの部屋に呼ばれたか、事情が飲み込めないという顔をしている。一方の水夫は歯が欠けていて、首筋は吹き出物で真っ赤だ。未来永劫こいつには手をふれないようにしよう。もう一人はハンサムで、柔らかそうな髪をしている。
「お前がドライデンだな?」あたしはハンサムの方に尋ねた。この船に乗り込んで何年にもなるので、古顔の水夫なら一人残らず知っている。だが、この色男は最後に寄航した港で雇ったばかりだった。そもそも雇ったのは親父だったので、あたし自身は詳しいことを何も知らないのだ。
「はい、船長」
「読み書きができると聞いた」
「はい、船長。僕の父親は...その...エラシアで書記をしていました。父と海に出ていたときに、<審判>が起きたんです」
「よし。お前たち二人に仕事を与える」そう言ってあたしは立ち上がり、テーブルの脇に回って角に寄りかかった。
「船倉に行き、ペンキを見つけてきな。色はなんでもかまわないよ。ペンキを見つけたら船尾に行って今の船名を削り落とし、新しい船名を書くんだ」二人はうなずいた。
船の名前を変えることは以前から決めていた。何事につけ独創性というものに欠けていた親父は、この船に<黒い死神>という名前をつけていたが、あたしは昔からこの名前が嫌で嫌でしかたがなかったのだ。
「なんという名前を書けばよろしいのでしょう、船長?」
「<猛き雌狐>だ」
「かしこまりました、船長」そう言うと二人は足早に退室した。
「全員、集合!海図に注目!」あたしは大声をはりあげ、船員たちが帆柱の周辺に集まれるよう、数歩下がった。
あたしは甲板に固定されていた木箱を演台がわりにすることにした。全員が海図を見終わるのを見計らって頭上で両手を振り、船員たちの注目をうながす。
「あたしを見な!あたしたちは何者だい?」
「海の男!」何人かが答えた。
あたしは首を振り、大声で言った。「陸を這っているつまらない豚どもと同じようなことを言うんじゃないよ!そんなカッコいいものかい?あたしたちは何なのさ?」
「犬だ!」
「クソ野郎だ!」
「盗っ人だ!人殺しだ!」
どれも間違ってはいない。だが、ついに一人が正しい答えを叫んだ。
「俺たちは海賊だ!」叫んだのは、がっしりしたあごをした低い男で、剃り上げた頭に塗られた油が太陽の下でギラギラ光っている。
この男の名前は”禿頭”アーノック、副長候補の一人だ。けんかの勝ち負けを予想する賭があったら、あたしはこの男に賭ける。アーノックの拳ときたらまるで岩のようだ。それに、痛みに強いことでも有名だ。二の腕にはピンク色をした生々しい火傷の跡があるが、これは相手よりも二倍長く炎の上に腕をかざしていられるかどうかを競うという賭けを繰り返してきた結果なのだ。これまでのところ、アーノックはこの賭けに負けたことがない。
アーノックは経験豊富な船乗りで、操船の腕も巧みだ。だが、信用して良いものだろうか?野心を抱くタイプには見えないが、女の部下になることをアーノックがどう思っているか、知る手だてはない。
「そうだ」あたしはアーノックを指した。さらに、全員に向かって大声で言った。「あたしたちは海賊だ!だけど、海賊はあたしたちだけじゃない。そうだな?ことわざにもあるように、<黄金海>に住んでいる海賊は魚より多いんだ!」
最後の言葉をかみしめる時間を与えるため、あたしは一呼吸おいた。それほど考えこむまでもなく、誰もが小賢しいスウィフト船長の手にかかって殺された親父のことを思い出したはずだ。実際、あたしたちの戦いの相手は、半分近くが商船ではなく商売敵だ。<黄金海>から本来なら得られるはずの利益をどの海賊も得ていないことに気づいたのは、もうずいぶんと昔のことだ。
「親父はもう歳だった。戦い方が古臭いだけでなく、考え方まで古臭くなっていた。だから親父は殺されたんだ!ここは新しい世界だ。新しい世界には新しい考え方が必要だ」
何人かが歓声を上げた。親父のことをこころよく思っていなかった連中だ。だが、あたしは本当に説得しなければならないのは、ブラック・バルフォアに長年忠実に仕えてきた、みんなから尊敬されている者たちだ。そう、”禿頭”アーノックのような。
「何がお望みで?他の海賊を皆殺しにすることですかい?」あたしの背後に視線を固定したまま、一人の船員が質問した。
「違う。それには時間がかかりすぎる。たしは<黄金海>を制服するつもりなのさ!」
今度は船員の大半が失笑した。無理もない。連中はあたしのことをまだ心から信頼していないのだから。だが、少なくともナメてはいない。
「どうやってです?」問うたのはアーノックだった。
「まずは<暴風海峡>を制圧する」あたしはマストに留めた海図を指しながら言った。
あたしがテーブルに向かっていると、若い水夫、ドライデンが船倉から戻って来た。ドライデンは持ってくるよう言いつけられたものをあたしの目の前においた。顔には困惑と少しばかりの恐れの表情が浮かんでいる。
「ご苦労、ドライデン。次はみんなのところに行って、あたしの言葉を伝えてくれるかい?」
「はい、船長。なんと言えばいいんでしょう?」
「副長になりたい者は、いますぐあたしに申し出ろ。そう言うんだ」
ドライデンが退室すると、あたしは最初の志願者への応対準備にとりかかった。誰が最初に部屋に入ってくるか、ある程度は検討がついていた。”禿頭”アーノックだろうか?それとも親父の下で副々長をしていた”八本指”のオバだろうか?
扉がギイっと開いた。入ってきたのは”斧使い”フォズだった。いかつい男で、筋肉がコブのように盛り上がっている。海賊になる前は兵士だっただけあって、部下たちの中でも指折りの猛者だ。そんな男を殺さなければならないとは、実に残念だ。
あたしはテーブルの下に隠しておいた石弓を放った。先ほどドライデンに武器倉から持ってこさせたのは、この石弓だったのだ。矢に貫かれたフォズは、船長室の扉に磔にされたような状態になった。フォズはうめき、矢に貫かれた箇所を手で押さえた。その愚かしい表情からして、明らかに自分の身に何が起きたのか理解していない。
あたしは足をテーブルに載せ、石弓のあぶみにつま先をつっこんで、弦を巻き上げた。
「副長になりたいかって言われてイの一番にかけつけるような野心満々の男は、野心的すぎて一緒の船に乗せておけないんだよ。悪いね、フォズ」
「あんたは...あんたは...」フォズは何か言おうとしたが、激痛は耐え難いほどだったに違いない。それでもフォズは愛用の斧をベルトから抜こうとあがいた。その根性だけは褒めてやらなければならないだろう。
あたしは二本目の矢をつがえ、フォズの胸に狙いを定めた。
「気休めにもならないだろうけど、船乗りらしくちゃんと水葬にしてあげるよ」
「親父さんに...したようにか!見たぞ...あのロープ...切れ目を入れただろう!」フォズは痛みに耐えるために食いしばった歯の間から言葉を絞り出した。そして、ようやくのことで斧を振り上げた。
「嫌ならいいさ。海に投げ捨ててやるよ!」
あたしは矢を放った。矢の威力はフォズを部屋の外まで吹き飛ばすのに十分だった。フォズはがくりと倒れ、絶命した。そこは遮る物のない船長室の外の甲板だった。
最初にかがみこんで死体を検分したのは”禿頭”アーノックだった。アーノックは無表情にあたしを見上げた。
「フォズは副長にふさわしくなかったようですな」
「ああ」あたしは答え、石弓をテーブルの上に置いた。壊れた扉が目にとまり、あたしは眉をしかめた。ちょうつがいの一つが外れてしまっている。
あたしはアーノックに視線を移した。「仕事を頼めるかい?お前にその気があるなら、の話だけど」
「そうですな。どうやら石弓は置いてこられたようだ。お引き受けしましょう」
小石が散らばる浜辺に降り立ったのはあたしが最初だった。陸地を踏みしめるのはひさしぶりなので、足下が揺れないことに違和感を感じる。船上での生活が長すぎた船乗りが陸に上がると、船酔いと同じ症状に見舞われることがあるが、あたしもすでに胃のあたりがムカムカしはじめていた。わたしは歯を食いしばり、むかつきがそれ以上ひどくなるのを必死に抑えこんだ。
あたしがここに来たのは、フリジストンへの陸路を見つけるためだ。それもこれも、フリジストンの長、”隻足”ジョーゴンが巨大な鎖を使って湾への侵入をたくみに防いでいるためだ。あたしに同行する者(全員が志願者だ)も船から降り、食料の入った袋や束ねた武器をきびきびとした動作で陸揚げしている。あたしたちは、フリジストン攻めに必要な物を、あるときは築き、あるときは奪いながら前進することになるだろう。
ゆっくりと、すべての上陸挺が<猛き雌狐>に帰っていき、最後に一隻だけが残った。その舟には新しくあたしの副長になった”禿頭”アーノックが乗っていた。
「あたしがいない間に勝手に船長名乗ったりしないって信じたいものだけど」
「約束はしかねますな」アーノックは不気味な笑みを浮かべた。いつもながら鳥肌が立つような笑みだ。
「あたしは約束するよ。おまえがあたしの船を奪ったりしたら、地の果てまでも追いかけて、八つ裂きにしてやるからね!」
アーノックはおかしそうに笑い、別れのしるしに手をふった。そうしている間も片手はオールを漕ぎ、力強く波頭を越えていく。普通は二人がかりでなければできない力技だ。はたしてあたしは<猛き雌狐>に再会できるのだろうか?
あたしは鞘から抜いた剣を頭上でふり、全員の注目をうながした。
「あたしたちが海の上での戦いを得意とする海賊だってことは百も承知さ。だけど、あたしと一緒にいるからには、乾いた陸の上じゃ戦えませんじゃすまないんだよ!ついてきな。もうすぐ<暴風海峡>はあたしたちのものだ!」
飼葉桶に満たした冷たい水に頭をひたしていると、二人の部下が近づいてきた。あたしは顔についた血を洗い落とし、したたる水でブラウスがぬれるのもかまわず、水を吸って重くなった長い髪を後ろにはねのけた。
「守備隊は皆殺しにしました。兵隊たちはお楽しみの最中です」副々長で、陸にいる間は「副官」の、”八本指”のオバが報告した。
オバは船乗りにしては長身で、ピンと張り詰めた筋肉と褐色の肌の持ち主だった。短く刈り込まれた黒いヒゲに白いものが混じり始めているが、オバが死んだ親父と同じぐらいの歳であることを窺わせているのはそれぐらいのものだ。オバは槍の達人だ。海賊になる前は何十年もクジラを獲って暮していただけのことはある。
「あまりハメをはずさせるんじゃないよ!フリジストンを攻略するためには、この町の資源が必要なんだからね」
「何であれ、直せないほど壊したりしないように、目を光らせておきましょう」
もう一方のピート・ガーリーという船乗りは、海賊にはふさわしくないほど優男だ。だからといって、こいつが弱いとか女々しいと思ったら大間違いだ。男らしくない点があるとすれば、それは腰までのばした柔らかな金髪ぐらいのものだろう。ピート・ガーリーは情け容赦を知らない戦士だ。なにしろ親父から仲間を罰する係を任されていたほどなのだ。親父が罰として鞭打ちを宣言すると、ピート・ガーリーが自慢の鞭をふるって刑を執行するというわけだ。実際、ピート・ガーリーの鞭さばきは巧みで、奴自身その役割を楽しんでいた。
あたしは手をのばし、自分を取り囲んでいる町を指し示すようにぐるりと体を回転させた。「盗賊と人殺しどもが素食うこの町は楽な獲物だった。統制がとれていなかったし、攻撃への備えもしていなかったからね。だけど、百戦錬磨の”隻足”ジョーゴンは違うよ。間違いなく準備をととのえているはずさ」
「奴らはバーバリアンです。戦うために生まれたような奴らです」こう言ったのは”八本指”のオバだ。
「以前、バーバリアンの船を奪ったじゃないですか」自身に満ちた口調でピート・ガーリーが言った。「奴らは小回りがきかないしバカだ。敵じゃありませんよ!」
「海の上ならな」それがオバの返答だった。
「そのとおり、陸の上で戦うことになるし、戦場はジョーゴンの領土だ。親父はろくなことを言わなかったけど’相手の土俵では絶対に戦うな’ってのは数少ない例外だね」
「ただし、親父は訓練を軽視しすぎていた。それが親父のバカだったところさ。そんなわけで、お前ら二人に兵隊の訓練にとりかかってもらいたいんだよ」あたしは急いでこう付け加えた。この二人にあたしの考えはすべて親父から受け継いだものだと思われるのが嫌だったのだ。
「どういう訓練です?」ピート・ガーリーが尋ねた。
「船員たちと徴兵できる奴らを誰でもいいから連れて、剣や六尺棒や斧、とにかくなんでもいいから手に入る武器の使い方を練習させるんだ!」
オバに対しては、「お前は他の連中、たとえばこの一帯に住んでいるオークどもを、射撃部隊として使い物になるようにするんだ。戦場で自分の足を間違って射抜くような間抜けはごめんだよ」と言った。
ピート・ガーリーは長い髪を指にクルクルと巻きつけた。
「やれと言われればやりますが、昔のエラシア兵のような錬度にはなりませんぜ。こんなクズ野郎たちをどんなに鍛えたってね」
「バカ、当たり前だ!誰がそんなことを期待するもんか!バーバリアンに立ち向かえればそれでいいのさ。すぐにくたばっちまってもかまわないんだよ。死ぬ前に敵を一人か二人は道づれにしてもらわないと困るだけさ」
つるや生い茂った藪をかき分けながら、あたしたちは内陸部を進んだ。道は皆無に等しかった。ここは無人の半島なのではないか?そんな気がし始めたとき、エルフどもが襲いかかってきた!
最初の一斉射で二人の新兵が倒れた。不用意に頭を上げた馬鹿者どもは、たちまち矢に射抜かれて命を落とした。あたひは剣を抜いたが、だからといって状況が改善されるわけではなかった。
「誰か奴らに近づけないか?」
申し合わせたように、一斉に「無理です」という答えが返ってきた。
対応に窮していると、副々長のオバが言った。「こうなったら<ドラゴンの一撃>しかないでしょう!」
<ドラゴンの一撃>とは海鮮で使う戦法の一つで、敵船のもろい横っ腹に必殺の体当たりをくらわせることだ。体当たりの衝撃によって敵が動揺している間に、ロープを架け渡し、斬り込み部隊を敵船に送り込むのだ。あたしたちに必要なのは、まさにこの最初の一撃だった!
「<ドラゴンの一撃>だ!やるよ!」あたしは部下たちに命じた。
次の瞬間、あたしは勢いよく立ち上がり、喉もさけよと絶叫した。ヒュッ、ヒュッと矢が体をかすめるが、体には気力が満ちてくる。たとえ矢が当っても、後になるまで当たったことに気づかないだろう。痛みは感じられない。あたしが感じているのは血への渇望だけだ。
少なくとも一人の射手が隠れていることを確認済みの木立を目指し、あたしは木がまばらになっている一画を走り抜けた。いた。怯えた青い目をしたエルフが、必死にベルトから短剣を抜こうとしている。あたしはそのエルフを容赦なく斬り伏せた。
「<ドラゴンの一撃>!」あたしは叫んだ。あたしにつづけという合図だ。このときのあたしは、「頼む、つづいてくれ」と祈るような気持ちだった。
左手の方角に何か気配を感じたあたしは、さっとそちらを向いた。あたしの目に飛び込んできたのは、樹上に身をひそめている射手の姿だった。射手は矢を長弓につがえなおそうとしていた。あたしは左手でナイフを引き抜いた。だが、腕に激痛が走り、あたしはナイフを落としてしまった。気が付かなかった。いつのまに手を射抜かれていたのだろう?
だが今はそんなことを考えている場合ではない。剣を地面に突き立て、あたしは右手でナイフを投げた。そして射手が地面に落ちる前に、すばやく剣を引き抜く。
間もなく、オバと部下たちがあたしのまわりに集まり、あたしを守りながら生き残っているエルフの掃討にとりかかった。
「勇敢でしたな、船長」オバが言った。
あたしは血まみれの左手をオバの目の前に差し出した。
「皆殺しだ!」
三百人以上の男が木を切ったり叩いたりする音が下から聞こえてくる。あたしは<ヤナズレーの絶壁>の端に立ち、はるか下の建設現場を見下ろした。<暴風海峡>に位置するフリジス湾の反対側の岸壁では、副々長である”八本指”のオバの監督の下、同じような光景が展開されているはずだ。
この調子で作業が進めば、船着場と造船所が完成するのは遠いことではない。この二つさえ完成すれば、<暴風海峡>制圧を確固たるものにする艦隊の建造に着手できるはずだ。水平線まで広がる蒼い大海原を見てあたしは微笑した。これはあたしのものだ!すでにあたしは親父にはたどり着けないほど遠くまで来ている。だが、ここでさえまだ終着点ではないのだ。
−−ブラディーコープ−−
| 詳細 | |
| 勝利条件: | スウィフト船長を倒す |
| 敗北条件: | タウニー・バルフォアまたはピート・ガーリーを失う |
| マップの難易度: | 「上級」ゲーム |
| 持ち越し: | タウリー・バルフォアとピート・ガーリー、および二人の呪文、技能、経験は、<<不壊の盾>>と一緒にすべて次のマップに引き継がれる。自軍の勇者の最大レベルは 18。 |
爆発が夜空をオレンジ色に染め上げ、ヤナズレーにいる者すべてを叩き起こした。あたしは、窓の外を見るまでもなく、音がしたから聞こえてきたことに気づいていた。船着場からだ。あたしはベッドから飛び起きた。
「何事です?」即座にピート・ガーリーが尋ねてきた。ベッドの上に身を起こした奴の手には、短剣が握られていた。まったく、どこにしまっていたんだか。
「服を着な!」剣帯に手をのばしながら、あたしは鋭い口調で言った。「動ける者全員を船着場に向かわせるんだよ!」
外にはすでに部下たちが半数ほどが集まっていた。”禿頭”アーノックもいた。”八本指”おオバも。よし!少なくともあたしの副長と副々長は非常時になすべきことを心得ている。だが、ここにいない連中にはお灸をすえてやらなければ。グズには罰が必要だ。
「アーノック!オバ!ついて来な!」叫びながら、あたしは門を目指して駆け出した。
門はすぐに開いた。あたしたちは非常用の通り道があるヤナズレーの断崖側へ向かって走った。船着場まで断崖を三百メートルほど下る、曲がりくねった長い階段を作っておいたのだ。しかし、たどり着くまでに何分もかかってしまう。そんな悠長なことをしている暇はない。あたしはオバが近道を作っておいてくれたことに感謝した。
断崖にたどり着いたあたしたちは、眼下の光景を見て動きが止まってしまった。二つの船着場と三つのドックが完成したのはほんの一か月前のことでしかない。そのドックが、新造した五隻の船もろとも、紅蓮の炎に包まれていた。
「行かないと!」
はるか下の浜辺まで一気に行けるポールに飛びつこうとするあたしの腕をオバがつかみ、何かを指し示した。
「あそこを!第二埠頭の端です」
ドックを焼き尽くそうとするお炎は、周囲を明るく照らし出していた。とも綱を解かれた小舟が、船着場の近くを漂っている。小舟が漂っていく先にはまだ無事な船の舳先が見えた。
いきなり小舟が爆発した!
火の玉は船着場と近くにあった船を飲み込み、さらに二隻の船に火をつけた。全員飲めが二隻目の小舟を捉えた。今度は第一埠頭に向かっている。最初の爆発の閃光から回復したあたしの目も、この第二の小舟を捉えていた。こちらの爆発のタイミングは、どうやら早すぎたようだ。先ほどの小舟く比べると、この小舟が与えた損害は小さかった。しかしそれでも港全体に火の粉が噴水のようにふりまかれた。
もはや一刻の猶予もならない。あたしは剣帯を非常用のポールにまきつけ、プラットフォームから身を躍らせた。絶壁が恐ろしいほどの速さで上に向かって流れ、浜辺がぐんぐん近づいてくる。スピードを落とさないと、着地のときに足を折ってしまう。クッションの山と砂があるとはいえ、たいした役には立たないだろう。あたしは歯をくいしばり、剣帯を引き絞った。皮が焼ける匂いが鼻を刺す。
下までは一瞬だった。最後の瞬間、あたしはクッションの山に飛び込んだ。それでも衝撃はすあsまじく、肺から空気が絞り出される。咳き込みながら、あたしはクッションの山から這い出し、立ち上がった。
正直に言えば、手遅れなのはわかっていた。あたりはすでに火の海だった。失敗しようのないほど周到な計画にもとづく攻撃だったことがうかがえる。
すぐにアーノックとオバも降りてきて、あたしの隣に立った。第一埠頭に目を向けたあたしが見たのは、まだ炎に舐めつくされていない一隻の船の姿だった。
「<猛き雌狐>を救うんだよ!」
それからの数時間、あたしたちは全力で消火作業にあたったが、船着場も、造船所も、艦隊も、すべてが失われてしまった。<猛き雌狐>だけはかろうじて生き残ったが、それでも修理に数週間を要するありさまだった。<猛き雌狐>は甲板が焼け焦げ、第一マストが爆発によって折れ、船体の各部が熱によって損傷していた。もちろん、死者の数も甚大だ。
かつては第一艦隊だった「もの」の残骸をあたしがじっと見ていると、主だった部下たちが集まってきた。
「いったい何が?」ピート・ガーリーが誰にともなく尋ねた。
「自爆船だ!」アーノックが答えた。「ブラック・バルフォアが数に勝るエラシア海軍と戦うのに、一度だけ使ったことがある。必要なのは上陸挺のような小舟だ。今回は釣り舟を使ったようだな。そこに<<悪魔火>>を満載する。あとは信管に点火して、敵に向けて流すだけだ」
「<<悪魔火>>ってのは何なんだい?」こう尋ねたのはあたしだ。
「カンテラの燃料の十倍は強力な爆発する液体ですよ。一種の魔法ですな」
オバが言い添えた。「何人ものアルケミストが調合法を悪魔から盗み出したと見えて、いまじゃどこにでもあります」
「敵の手口はわかった。だけど、あたしが一番知りたいのは、誰がやったかだよ。ピート・ガーリー、お調べ!」
自爆船を仕える距離まで敵を招き入れたのは、歩哨に立っていた二人の船員だった。そのうち一人は口封じのために敵に殺されてしまっていたが、もう一人はその場を逃れていた。あたしたちにとっては幸運であり、裏切り者にとっては不運な成り行きだ。
ピート・ガーリーが裏切り者から話を聞き出すのに、ものの十五分もかからなかった。この手のことにかけて、ピートの右に出る者はいない。その結果、実に興味深いことが分かった。スウィフト船長が、あたしの<暴風海峡>制覇を邪魔するため、今回の攻撃を指揮していたのだ。たしかにあたしが<暴風海峡>を支配したら、奴にとっては死活問題だろう。フリジストンからの知らせはまだだが、裏切り者の話によると、スウィフト船長は北にある造船所に対しても同じことを計画しているらしい。このままだと、少なくとも海に関する限り、あたしは遠からず丸裸にされてしまう。
あたしの人生に再びスウィフト船長という名前が登場したわけだ。ただし、今回は憎い敵として。スウィフト船長があたしの親父を殺したのが奴との馴初めだ。あれは海賊同士の戦いとしてはこれ以上ないほど正々堂々とした戦いだった。だから今日まで、あたしはスウィフト船長に特別な敵意は抱いていなかった。それどころか、あたしの艦隊に加わらないかと彼に問う日だって、いつか来たかもしれないほどだ。だが、それは過去の話になった。スウィフトのやつ、このまま生かしてはおかないよ。
あたしは<猛き雌狐>の修理と造船所の再建を命じた上で”禿頭”アーノックにヤナズレーの指揮をゆだね、自分はオバとピート・ガーリー、それに少数の手勢を率いて南に向かい、スウゥフト船長の隠れ家、ブラッディーコーブを探すことにした。
まだ誰も目を覚ましてない早朝、あたしは<黄金海>を見つめていた。そんなあたしに気づき、オバが近づいてきた。そのときのあたしの心を占めていたのはスウィフト船長だった。あたしは彼と会いまみえる瞬間のことをとりとめもなく考えていた。一瞬、あたしはオバを追い払おうかと思ったが、オバの口から出た言葉はあたしの関心を引くのに十分なものだった。
「自分が勝てると思わない限り、スウィフト船長は戦わんでしょう」
「望むと望まざるとに関わらず、あいつはあたしと戦うことになるさ。あいつに選択権を与えるつもりはないからね」
「スウィフト船長を戦いに引きずりこむことはできないだろうと申し上げているんです。スウィフト船長の本拠地であるブラッディーコーブで戦いを挑まなければならないでしょうな」
「あたしのことなら心配いらないよ。あたしはブラッディーコーブに落とし前をつけさせる。後に残るのは黒く焼け焦げた大地だけさ」
「船が必要不可欠です。聞くところによると、スウィフトは<アサシン>の甲板を滅多に離れないとか」
あたしはうなずいた。だが、この地方には数多くの海賊やならず者が隠れ住んでいる。その中には船を持っている奴がきっといる。船のことは心配に及ばない問題だ。
「ブラッディーコーブがどこにあるか、誰か知っている奴はいるんだろう?」
「いるとしても、それがどういう奴かとなると...元船乗り、スウィフトに物資を売ってる商人、売春婦...可能性の話をすれば数限りない!」
最近はこうしてスウィフト船長の話をしていると、以前に一度だけ本人にお目にかかったときのことが思い出される。親父が殺された日のことだ。記憶にあるスウィフトは、ひきしまった体つきをした男で、歳は三十代、よく手入れされた茶色のくちひげを生やし、髪を後ろで束ねて短いポニーテールにしていた。燃えるような真っ赤な上着、それに戦うときに持っていた剣と短剣もよくおぼえている。
当時、親父は三隻の船を率いていた。親父自身の旗艦である<黒い死神>と、より俊足な二隻の小型船だ。一年前のあたしは<稲妻の亀裂>の指揮をとっていた。船を任されたのはこれが初めてで、親父としてはあたしが自分のかたわらで戦うのにふさわしい力があるかどうか試すつもりだったのだろう。<黒い矢>は完成したばかりで、スケルトンどもが操っていた。
海賊の港として有名だった<黄金海>南部の港に向かっていたあたしたちは、水平線に二つの帆を発見した。それから数時間、親父はこの二隻の船の周囲を帆走し、どういう素性の船か見きわめようとした。あたしは作戦会議に出なかったが、あとから”八本指”のオバが教えてくれたところによれば、オバとゴリー・ゴーディーは手を出すべきではないと進言したらしい。<黒い矢>には航海するのに最低限の乗員しか乗っていなかったのだから無理もない。
だが、ブラック・バルフォアは他人の意見を聞くような男ではなかった。
親父は攻撃命令を下した。三対二なら十分に勝てるとふんだのだ。きっと親父は相手を積荷を満載した商船だと信じ込んでいたのだろう。だが、本当に相手が商船だったらどうするつもりだったのか、いまだにあたしにはわからない。<黒い死神>の船倉はすでに満杯だったし、<黒い矢>も同様にかなりの荷を積んでいたのだ。
とにもかくにも、あたしたちは二隻の進路を遮るコースを算定しつつ、攻撃にとりかかった。まず、二隻は北を目指して逃げた。だがこれは親父の予想の範疇だった。次に二隻は西に進路を変えた。あたしたちに追いつかれる前に、安全な港に逃げ込もうというのだろう。あたしはそう思った。空荷だったあたしの<稲妻の亀裂>が先行した。最初の罠に気づいたのもあたしだった。
さらに二隻の船が水平線に現れ、帆を張った。親父は海賊が大昔から使っている罠にはまったのだ。あたしたちが追いかけていた二隻の船は、鈍足で荷物を満載しているように見せかけた餌だった。一方、新手の二隻は、喫水線が高く、そのうえ帆をたたんでいた。よほど近づかなければ存在に気づかず、気づいたときにはすでに手遅れというわけだ。あたしたちはまんまと罠にかかってしまった。戦う以外、選択肢は残されていなかった。
<稲妻の亀裂>の俊足をいかせば、逃げ出すことも不可能ではなかったかもしれないが、それでは<黒い死神>と<黒い矢>が格好の獲物になってしまう。あたしは、敵の待ち伏せを台無しにできないか、いちかばちか賭けに出ることにした。あたしは<稲妻の亀裂>の進路をこの二隻の小型船に向けさせ、攻撃を命じた。あたしたちが追いかけていた二隻の面倒は、親父に見てもらうしかない。
海戦とは操船において敵を圧倒することに他ならない。こちらには左舷と右舷にバリスタが三基ずつ、船首と船尾に小型のカタパルトが一基ずつある。この武装と快速が、<稲妻の亀裂>を小さいながらも恐るべき船に仕立てあげていた。戦闘開始からものの数分で一方の敵船に<稲妻の亀裂>を横づけすることに成功したあたしは、帆を狙ってバリスタを放つように命じた。幸運な一撃が一本しかないマストを折り、敵船から航行能力を奪った。
だが、敵もさるもの。一隻を行動不能にした直後、もう一隻のカタパルトから放たれた鉄球が、<稲妻の亀裂>の甲板を粉砕した。これによって浸水が生じたが、くみ出せないほどではなかった。それから一時間、我々はなんとか相手より優位に立とうと、必死の操船をつづけた。そしてついに二隻の船は激突した。こちらを出し抜くことに成功した敵が、<稲妻の亀裂>の横っ腹に体当たりしてきたのだ。足の下で船体がきしみ、ギーギーと気味の悪い音を発した。この船はもうすぐ沈む。あたしはそう悟った。
「野郎ども、剣と短剣の準備だ!」自分自身、券を抜きながら、あたしは叫んだ。「豚どもを八つ裂きにするんだよ!」
戦いが終わったとき、部下の数は最初の四分の一に減っていた。<稲妻の亀裂>は急速に沈みつつあり、敵船も一緒に海の中に引きずり込まれようとしていた。あたしたちは上陸挺を海面に降ろし、<稲妻の亀裂>を放棄した。その後、あたしたちにできるのは、残る二隻と<黒い死神>の戦いを見守るだけだった。<黒い矢>の乗組員たちに戦いに加わる石がないことは明らかで、さっさと逃げ出してしまっていた。親父とあたしが敵と戦っている間に安全な場所まで脱出するつもりなのだろう。
<黒い死神>はスウィフト船長の船、<アサシン>と戦いを繰り広げた。あたしと同じように互いの船体を平行にすると、ブラック・バルフォアは乗組員たちに敵船に乗り込んで白兵戦を挑むことを命じた。だが、船を守るために船員たちの陣頭にたったスウィフト船長は、二本の剣をふるってやすやすと親父の部下たちを撃退した。親父が前線に出てスウィフト船長に挑みかかったとき、すでに戦いの決着はついていた。それぐらい味方の損失は大きかったのだ。
だが、この最後の戦いはそれなりに見応えのあるものだった。胸に深々と短剣を突きたてられても、ブラック・バルフォアは激しく戦いつづけた。だが間もなく、血を失いすぎた影響があらわれ、ブラック・バルフォアの守りに大きな隙ができた。それを見逃さず、スウィフトは親父の心臓を剣で貫いた。
お互い、損失があまりにも大きすぎた。戦いをさらにつづけて自分自身も回復不能の痛手をこうむることを恐れ、スウィフト船長は退却した。追撃は行われなかった。船長、つまりあたしの親父であるブラック・バルフォアが殺されたという知らせが行き渡ると、誰もが戦意を失ってしまったからだ。
あたしのお袋はタダ同然の安月給でこき使われていた酒場女だった。昔、あたしは自分の親父が誰なのか知らなかった。親父は一度も姿を見せなかったし、お袋は親父の名前をけっして口にしようとしなかったからだ。
あたしはお袋と一緒に<錆びたジョッキ>亭で働いていた。床を拭いたりテーブルまでパンを運んだりすることがあたしの仕事だった。<錆びたジョッキ>亭はナイオン海岸の小さな港町にあり、客の大半はエラシアの法から逃れてきた盗賊や海賊だった。ちょっとした口論が原因で人が刺し殺されるのは日常茶飯事だったが、あたしにとって面倒でしかたがなかったのは、床にぶちまけられた血を掃除しなければならないことだった。
ある夜、首のまわりに蛇の刺青をした赤毛の海賊が来て、普通の客よりも長くお袋と話しこんでいた。二人は笑い、何時間も飲みつづけた。お袋がそうして仕事をさぼっているせいで、あたしはいつもより一生懸命働かなければならなかった。
夜もふけた頃、赤毛の仲間の水夫が席を蹴って立ち上がった。水夫は激昂していた。
赤毛と水夫はどちらも短剣を抜いた。お袋が殺されるんじゃないかと思って怖かったことをおぼえている。だが、勝負は一瞬でついた。勝ったのは赤毛だった。駆け寄ろうとしたあたしに、お袋は雑巾を握らせ、バケツを持ってくるように言いつけた。
あたしは這いつくばって床を汚した血を拭いた。死体は誰かが店の外に運び出してくれた。お袋は二階にしけこんで姿を見せない。あたしの中で何かが変わった。
七歳のときのことだ。
十歳のとき、あたしは初めて親父に会った。もっとも、そのときはそれが親父だとわからなかったのだが。あたしがおぼえているのは、みんなが口々にブラック・バルフォアという名前をささやき、その姿に熱いまなざしを向けていたことだ。なぜこの人はこんなに人気があるんだろうと、当時のあたしはいぶかしんだものだ。ブラック・バルフォアは愛想がよく、金を惜しまなかった。この晩だけでもブラック・バルフォアは、店にいた客全員に三回も酒をおごった。
夜もふける頃、ブラック・バルフォアはお袋を街に連れ出した。なんという運命のめぐり合わせだろう。この逞しくて金持ちの海賊が自分の親父で、自分をここから連れ出して威風堂々とした海賊船に乗せてくれたらどんなに素敵だろうと夢想したことを、あたしは今でもはっきりおぼえている。そうだ。どん底の生活を送っていたのに、それでもあたしはロマンチストだったのだ。
朝、あたしが店の掃除をしていると、ブラック・バルフォアが階段を降りてきた。ブラック・バルフォアは樽を一つ持ち上げ、カウンターに硬貨を一枚置いた。それからあたしの方にゆっくりした足取りで近づいてきた。
「よく働くじゃねえか。名前はなんてんだ?」
「ダウニー」あたしはすぐに返事をした。
「へっ!酒場女の名前だぜ」
あたしは肩をすくめるだけで精一杯だった。憧れの人が目の前にいることに舞い上がって、どんな言葉も出てこなかったのだ。
「短剣は持ってるか?」
あたしは首を横にふった。するとブラック・バルフォアは懐に手を入れ、細身の長いナイフを取り出した。
「このままいけば、お前も母ちゃんみたいな器量よしになりそうだからな」そう言ってブラック・バルフォアはあたしにナイフを手渡した。ナイフは重くて冷たかったが、柄の握りごこちはあたしの小さな手にあつらえたかのようにしっくりきた。
「こんなヤバい場所じゃあ」ブラック・バルフォアは喋りつづけた。「器量がいいってことは災難のもとだ」
ブラック・バルフォアはあたしと目の高さが同じようになるように膝をつき、ニカっと笑った。前歯のうち二本が金歯だった。
「嫌な奴に体をさわられたり、すけべな目で見られたときは、思い知らせてやれ!このナイフはな、あばら骨の間に滑り込ませて心臓を一突きするのに最高なんだ。豚か何かで少し練習しとくんだな。それと、普段は隠しておいて、お前がそんな物を持ってるとは誰も思わないようにしとけ。相手の不意を突くってのが、最高の戦法なんだ」
親らしいことをしてくれたのは、後にも先にもこのときだけだったが、このときほど嬉しかったことはない。それだけは認めざるをえないだろう。このときのナイフは今でも持っている。親父の副長だったゴリー・ゴーディーを殺すのに使ったのもこのナイフだ。
一週間後、あたしはお袋からブラック・バルフォアが親父だと知らされた。
二年後、あたしはお袋と縁を切り、<錆びたジョッキ>亭で働くのもやめていた。ある晩、酔っ払ったお袋が、この街にはお前の親父違いの兄がいると漏らしたのだ。ノリーは父親の家で暮らしていた。何年もの間、このことをお袋が隠していたという事実は、あたしを激怒させた。あたしはお袋に騙されていたのだ。
あたしは家出してノリーに会いに行った。ノリーの父親は船乗りで、たまには海賊にもなるという男だったので、ひとたび船出すると何ヶ月も家を留守にすることがあった。継母はノリーを嫌っていた。継母にとってノリーは夫の不貞の証拠なのだ。この話を耳にしてあたしは喜んだ。ノリーもあたしと同じようにつらい子供時代を過ごしたのだ。あたしたちは同族だ。離れ離れになっていた同族が、ようやく再会できたのだ。
あたしより二歳年上だったノリーは、若い連中だけで構成された小さな盗賊団の一員だった。ノリーはすぐにあたしを仲間に加え、ロープの扱い方を教えてくれた。あたしたち二人のどちらにとってもあれは幸福な時期だった。あたしたちは空腹を癒すために盗み、空腹が癒されると自分たちの力をためすために盗んだ。あおの頃のことを思い出すと、今でも自然に笑みがこぼれてくる。
しかし、あたしたちが一緒にいられた時間は短かった。たったの二年だ。ノリーは他の連中と一緒になって、強盗の計画を立てていた。だが、ノリーは無鉄砲で、立てる計画はいつも細かいところが雑だった。あのときも計画を他人任せにしていたのだろう。馬鹿なノリー。自分から罠に飛び込むなんて!
翌日、路地裏でノリーの死体が見つかった。ノリーは背中を七箇所も刺され、その死体はネズミにかじられるままに放置されていた。
何ヶ月もかけてあたしは、ノリーを裏切ったのはノリーの相棒で、殺したのは七年間に七回もノリーに押し入られた商人だということを調べ上げた。商人は自分の正しさを必死に主張した。
その商人はあたしも知っている男だった。七回のうち二回は、あたしもノリーと一緒に押し入ったのだから。親父からもらったナイフを使い、あたしは商人をたっぷりといたぶってやった。それがすむと、あたしはノリーを裏切った奴をおいつめ、ナイフの柄で殴って気絶させた。あたしは確かに悲鳴を聞きつけられる心配のない郊外に裏切り者を運び、縛り上げ、七匹の飢えたネズミが入っているジャガイモの袋に顔だけ外に出した状態で詰め込んだ。
ノリーの仇が死ぬのにたっぷり一時間以上かかった。
スリはまったくもうからない。押し入り強盗は用心棒がいると厄介だ。そんなわけで、ノリーの死後、あたしは盗賊としての自分の才能を、追いはぎをしていかすことにした。あたしは自分が頭目となって盗賊団を結成し、待ち伏せするのに絶好と思われる場所を街道沿いに見つけた。
ある日、戦利品のネックレスを首にかけ、財布を黄金で膨らませて町に帰ってきたあたしは、三日前にお袋が死んだことを知らされた。
どうしてお袋の末路を知るために<錆びたジョッキ>亭に足を運んだのか、いまでもよくわからない。だけど、確かめなければ気がすまなかったのだ。ひさしぶりに会った亭主は、何ヶ月か前からわずらっていた病気がついに命取りになったのだと教えてくれた。
「あいつの面倒は全部、俺が見てやったんだぞ」看病をした礼金をよこせということらしい。
「そいつはご愁傷さま」そういってあたしはきびすを返した。
「おい!葬式代も出さないつもりか?」
「もう死んでんだよ。どうしようと関係ないじゃない?海に放り込めばそれで十分さ!」
お袋にとって自分がいらない子供だってことは生まれたときからわかっていた。それでもお袋はあたしを捨てたりしなかった。親父と対面したのはナイフをもらった日が最初だ。間違ってもあたしを引き取ったりはしないだろう。
それとも引き取ってくれるだろうか?親父は有名人で、当代随一の海賊の一人だ。大エラシア王国でさえ、親父を恐れているのだ!
それに今のあたしは、ほうきの使い方しか知らない役立たずのチビじゃない。短剣の技とスピードにかけてあたしの右に出る者はほとんどいないし、剣の腕前だってかなりのものだ。今のあたしなら親父の船に乗せてもらえるかもしれない。
<審判>の混乱の中、<門>を抜ける船に乗ることができた幸運な者になりすますのは、あたしにとって雑作もないことだった。あたしは男と同じように働いた。当時、あたしは十七歳だったが、腰の右側には宝石が入った小袋、左側には剣をつるし、左の袖には親父からもらったナイフを仕込んでいた。この新世界がどんな場所であろうと、何とかやっていく準備はととのっていたのだ。
それどころか、旧世界とおさらばできて、むしろ嬉しかった。古い記憶とも別れることができたからだ。
あたしは<黄金海>の海岸にある新しい町に腰を落ち着けた。その町の雰囲気が故郷にあまりにも似ていたので、あたしは面食らってしまった。何ヶ月もの間、あたしは何とか海賊船の船員にしてもらおうと悪戦苦闘したが、若すぎるとか女は駄目だといって断られてばかりいた。職を得るために、あたしはかなりの賄賂を使わなければならなかった。
ようやく見つかった職場は快適だった。航海長があたしに優しかったのをいいことに、まずは操船のやり方を、次には読み書きを教えてもらった。それから二年間で、あたしは船乗りと海賊に求められることをすべて修得したが、受けて然るべき敬意だけは得ることができなかった。
そんなわけで、ある港に寄港したのを潮時に、あたしはその船を降り、最後に残ったわずかな金をにぎりしめて手近な宿屋に足を踏み入れた。するとなんということか、親父がゴリー・ゴーディーやオバ(当時はまだすべての指があった)と一緒に座っているではないか。
こうしてブラック・バルフォアと偶然に再会したのは運命なのだ。この好機を捕まえようとすることなく逃すわけにはいかない。
あたしは親父のテーブルに近づき、親父があたしを見てくれるまで待った。親父はウィンクを一つよこしたが、あたしが誰かわかっていない様子だった。
「あたしはタウニー・バルフォア。あなたの娘よ」
「ほう!」親父はそれしか言わなかった。
「海賊なの。父さんと同じくね。仕事を探してるのよ」
「お嬢ちゃん、<黒い死神>には今のところ一人の欠員もなくてね。空きはないんだよ。職探しなら他をあたりな」
胃が締め上げられるようだった。意識してなかったが、まさか拒絶されるとは思っていなかったのだろう。次の瞬間、全身が怒りで熱くなった。お袋と同じように、ブラック・バルフォアまであたしを邪魔者あつかいしている。それ以上に、父親と一緒に大海原を駆け巡るなんていう子供じみたおめでたい夢を何年も追いかけてきた自分自身に腹が立った。
ゴリー・ゴーディーが手をのばし、あたしの尻をなでまわした。
「俺ならお嬢ちゃんを船に乗せてやれるぜ」
抜く手も見せず、あたしは親父がくれたあのナイフでゴーディーの左の耳たぶを切り裂いた。痛みに絶叫しながらゴーディーが椅子を蹴って立ち上がった。お互いに腰の剣に手をのばす。だが、その働きは親父がクックックと笑い出したことで止まった。加勢してもらえないのが意外だったゴーディーは親父の方を見た。ゴーディーがあたしに憎しみを抱いたのは、きっとこの日だろう。
ブラック・バルフォアは立ち上がり、あたしの肩をポンと叩いた。
「俺に言われたことを、ちゃんとおぼえていたようだな」
あたしは親父にほほ笑みかえしながら言った。「嫌な奴にはさわらせないわ」
「その心意気だ。だが、悪いな。船員に空きがないのは本当だ。また、機会があったらな」
そう言うと親父はオバとゴーディーを引き連れて宿屋から出て行った。
あきらめは何も生み出さない。
あたしは親父の船、<黒い死神>を見つけ、それから二週間はこの船ばかり見てすごした。<審判>が親父に深手を負わせたことはすぐにわかった。かつては六隻の艦隊だったのに、今や生き残っているのは<黒い死神>だけなのだ。これまでに蓄えた財宝もすべて失っていた。一介のしがない海賊に戻ってしまった親父は、失ったものを取り戻そうと必死だった。
数年後、周囲の反対を押し切って親父は無力に見えた二隻の船を襲い、スウィフト船長の罠にはまってしまうことになるのだが、無理をした理由はこのあたりにあるのだろう。
ある日、<黒い死神>が出港準備をととのえていることに気づいたあたしは、真夜中になるのを持って<黒い死神>に忍び込み、船倉に身を隠した。
今になって思えば、なんと子供じみていて愚かだったことか。もし密航者を見つけたら、あたしはどうするだろう?おそらく親父と同じようにするだろう。
ある夜、ついにあたしは見つかり、親父の前にひきすえられた。あたしは悪びれることなく胸を張っていた。水夫たちはあたしから武器と金をとりあげ、あまつさえブーツまで脱がした。
親父は不機嫌きわまりない顔で、自分の前にひざまずかされているあたしを見た。
「馬鹿な娘だ!」そう言って親父はあたしの頬をはった。
親父の力がどれほど強いか、あたしはこのとき初めて知った。数秒間、意識がもうろうとなってしまったが、こういう荒っぽい仕打ちには馴れっこだ。とはいえ、ものの数秒もすると、まぶたがはれて、片目がよく見えなくなってきた。
「父さんの船に乗りたいのよ」怒りをかみ殺しながらあたしは言った。「誰か連れて来て!誰でもいいから!そいつを殺して仕事を奪ってやる!」
だが、親父はあたしを無視して、考え込むような表情で暗い海面を見つめた。
「しばり首にしますか?」ゴリー・ゴーディーが親父に尋ねた。そうなることを願ってるような、はずんだ口調だった。
「いや」そう言って親父はあたしの命を救ってくれた。どんなに憎んでもあきたらない親父だが、少なくともこのときの判断は尊敬に値すると思う。
「海に放り込め。それが妥当だ」ブラック・バルフォアはそう命じた。
親父はゴリー・ゴーディーと何人かの水夫があたしを船べりまで運んでいくのを見守っていた。ゴーディーたちは歓声を上げ、あたしの手と足を持ち、一、二の三であたしを放り投げた。真っ黒な海に落ちたあたしにゴーディーたちは唾をはきかけ、<黒い死神>はゆっくりと闇の中に消えていった。親父は海に落ちたあたしを見に来ようとしなかった。
立ち泳ぎしながら、あたしはどうすべきか必死に考えた。ここは沖合いだ。陸地までとても泳げるものではない。このままでは確実に死ぬ。いっそのこと力の限り深くもぐって、水を思いっきり飲み込んでやろうかとも思ったが、自殺なんて論外だ。自殺するのは降参するのと同じことだ。あたしは降参だけはしないのだ!
凍えそうになりながら、あたしは一晩中そこに浮かんでいた。力が入らなくなっていたが、それでもあたしは足で見ずを蹴りつづけた。すると水平線に朝日がのぼってきた。最初、太陽の光はありがちものに思えた。だが、やがて強い日差しはあたしの肌を焼き、目をくらませた。それでもあたしは音を上げなかった。
日が沈んだとき、あたしは覚悟を決めた。再び朝日を見ることはないだろう。もうすぐあたしはノリーのところへ行くのだ。あたしたちのような人間が死後どこへ行くのかはわからないけど。
「世界よ、呪われろ!お前はいつだってあたしを殺そうとしてきた。お袋、<錆びたジョッキ>亭、子供時代!あたしはそのすべてを生き延びた!だけど、そろそろお前が勝つときがきたようだ」天に向かってあたしは叫んだ。
夜がやってきた。寒い。暗い。ときどき頭まで波をかぶってしまう。あたしを呑み込もうとする海へのささやかな反抗として、あたしは足で水をかく回数を数えはじめた。
意識が混濁し、ありもしないものが見えはじめた。夜空が明るくなったような気がする。だが、太陽が昇ったわけではないようだ。まるで巨大な黒い獣のように、ちらちらと瞬く光に囲まれた漆黒があたしの頭上に覆いかぶさってきたような感じだ。これも幻なのだろうか?
誰かが叫んだ。「おーい、右舷だ!」
なぜかまた波が高くなりはじめ、あたしにうち寄せてきた。あたしの体を海中に引きずり込もうとする。ああ、そうか。このあたりの海を統べる神が、あたしの命を欲しがっているのだ。
あたしは海から引き揚げられ、固い甲板の上に放り出された。誰かがあたしの頬を叩いた。
「まったく運のいい娘だ!」
「冗談じゃない。最悪よ」
ふやけたあたしの手に馴染みのある金属の柄が押しつけられた。あたしのナイフだ。はれていない方の目を必死の思いで開いたあたしが見たのは、親父のヒゲ面だった。
「欠員はない」親父はささやくように言った。「この船に乗りたいなら、自分で居場所を作ることだ」
あたしは他の海賊たちの顔を見回した。残念ながらゴリー・ゴーディーはその場にいなかった。しかたなく、立ち上がったあたしは、最後の力を振り絞って手近にいた男にナイフを投げつけた。次の瞬間、あたしは甲板に崩れ落ちていた。精根尽き果て、もはや指一本動かせなかった。誰かがあたしのとなりにドサっと倒れてきた。
こうしてあたしは<黒い死神>の一員になった。
ついにブラッディーコープにやって来た!優雅に波に揺られているのは<アサシン>だ。あの美しい船なら、あたしはどんなに離れていても見分けることができる。
剣を抜き、切っ先で<アサシン>を指し示しながら、あたしは叫んだ。「あの犬どもに教訓ってやつを教えておやり!皆殺しにするんだ。ただし、スウィフトにだけは手を出すんじゃないよ。あいつはあたしの獲物なんだからね!
−−帰らずの海峡−−
| 詳細 | |
| 勝利条件: | ランボートに<混沌の目>を築く |
| 敗北条件: | タウニー・バルフォア、ピート・ガーリー、ランボートの町のいずれかを失う |
| マップの難易度: | 「上級」ゲーム |
| 持ち越し: | タウリー・バルフォアとピート・ガーリー、キルカ、および三人の呪文、技能、経験は、<<ジャイアントスレイヤー>>と一緒にすべて次のマップに引き継がれる自軍の勇者の最大レベルは 23。 |
「このところ、あたしの運はどうしちまったんだ?」目前でまたも船が沈んでいくのをなすすべもなく見守りながら、あたしは嘆息した。
二週間前、あたしは<黄金海>全域の制覇を成し遂げるため、七隻の船で構成された艦隊を率いて、ヤナズレーを出発した。<黄金海>の制覇は、<帰らずの海峡>の制覇なくしてありえない。だが、この海域がこんな不吉な名前をたてまつられたのは、故なきことではないのだ。親父でさえここには近づこうとしなかった。過去にここでは多くの船が消息を絶っている。そして今、あたしは初めてその理由を知ったというわけだ。
あたしたちは警戒しながら<帰らずの海峡>に侵入した。何を警戒すればいいのかはわかっていなかったが、まさかシーモンスターがひそんでいたとは。
最初の怪物は艦隊の背後から襲いかかってきて、しんがりをつとめていた船を転覆させた。このいきなり現れた脅威に対処するために他の船が回頭し終わったときには、転覆した船は乗組員もろとも波間に沈んでいこうとしていた。あとは完全な乱戦になった。
”八本指”のオバはsっと銛をつかみ、<猛き雌狐>の舳先に陣取った。あたしは船をシーモンスターに向けさせ、船員たちに大声で命令を発した。舷側と船尾に弓兵を配置し、噂どおり怪物が甲板に飛び乗ってきた場合にそなえて槍兵を護衛につける。
シーモンスターは予想のつかない相手だが、抵抗されるとすぐに攻撃をあきらめるのが普通だ。だがこの日は違った。怪物が頭から船体に激突し、二隻目の船が真っ二つになった。戦況は刻々と我が方にとって不利になりつつあった。
”禿頭”アーノックが指揮をとる<破壊神>が怪物に挑みかかっていく。そのとき、あたしの船の右舷に海面を割って怪物があらわれた。
「二匹だ!二匹いるぞ!」シーモンスターが連携して襲いかかってきたなどという話は聞いたことがない。この海域は何かがおかしい。だが、深く考えている余裕はなかった。
最終的には、シーモンスターは撃退された。部下たちのおかげだ。彼らはじつによく戦ってくれた。だが、勝利をおさめるまでにあたしたちはさらに三隻の船を失ってしまった。<破壊神>はなんとか生き残ったが、船体に大きなダメージを負っていた。
ポート・ガーリーは今もあたしのかたわらにいる。アーノックにも船を任せてからは、ピートが<猛き雌狐>の副長だ。
「二十八人を海から引き上げました。他の奴らは今ごろ海の底か、さもなければ怪物の胃袋の中です」
ピートの報告を聞き、水平線を望遠鏡で見張りながらあたしはうなずいた。あの攻撃は何か統制がとれていたような気がする。二匹の怪物は連携して戦い、死ぬことを恐れていなかった。どう考えても妙だ。誰かが怪物を操っていたという可能性はないだろうか?
そのとき、水中に金色のものが見え、それにつづいて尾びれがキラキラと光った。見えていた時間は一秒にも満たなかったが、それが何であるか、あたしは即座に悟った。
「人魚だ。これで合点がいった!」
「人魚がどうしたってんです?」
「あの歓迎パーティーを開いてくれたのは人魚だって言ってるんだよ」
そう言ってあたしはピートに望遠鏡を渡した。
数ヶ月前、あたしは何人かの部下を陸路でこの地に派遣し、ランボートという名の前哨地を築かせた。この<帰らずの海峡>であたしの拠点になるべき場所だ。だが、派遣した部下たちからの連絡は途絶えたままになっていた。だからこそあたし自らが七隻の船を率いてきたのだ。力を誇示することがあたしの狙いだった。正直に言って、あたしは正体不明の敵の力をみくびっていた。同じ失敗は二度とすまい。
人魚たちがどう思おうと、あたしがここに来たのは<帰らずの海峡>に面した港町を築くためだ。人魚だろうと海賊だろうとシーモンスターだろうと、あたしの邪魔はさせない。
ピート・ガーリーだけをともなって、あたしは蒸し風呂のような原生林を進んだ。ランボートがすぐ近くであることはわかっていたが、軍勢をともなって接近する前に、一目見ておきたかったのだ。
半島の先端に位置するここは、港を築くのに理想的な場所だ。それに、陸から少し離れただけで水深が急に深くなっているので、どんな大きさの船であっても投錨することができる。派遣した部下たちはいい選択眼を持っていたようだ。おしむらくは防備に手抜かりがあった。生きていれば、たっぷりと褒美をやったのに。現在でさえ、ランボートは湿地に立てられた掘っ立て小屋の集まりに毛が生えた程度のものでしかない。こんなところを手に入れるために殺し合いをする奴がいるのだろうか?
長い杭の先に串刺しにされたいくつもの死体が目にとまり、あたしは足を止めた。ときおり、カラスどもが餌にありつきに来る。後に残るのは、じっとあたしを見つめる不気味な骸骨だけだ。
あたしはこの死者たちのことが無性に気になった。別に恐ろしかったわけではない。これぐらいの脅しに怯むあたしではない。じっと見ていると、あたしの旗が目にとまった。どうやらこいつらはあたしの部下のようだ。旗は一体の骸骨の首にまとわりついていた。ひどく汚れ、ボロボロになっている。わかった!こいつらは前哨地ランボートを築くために派遣した者たちのなれの果てだ!
「ふむ」感心なさそうな口調でピート・ガーリーが言った。「どうやら、今、ランボートを仕切っているのは、我々以外の誰かのようですね」
「ああ。だが、それも長いことないさ」あたしは絞り出すような声で言った。誰がこんなまねをしたかは知らないが、勝利を誇示しようというのだろう。あたしの逆鱗にふれてしまったことを思い知らせてやる。
あたしは死体を指して叫んだ。「降ろしてやれ!」
今朝は槌で木を叩く音に起こされた。どこへ行っても人々が急がしそうに働いている。仕事を監督しているのは副々長である”八本指”のオバだ。
「ご苦労。お前のおかげでみんなが一生懸命働いているよ」
「俺の手柄じゃありませんよ、船長。ピート・ガーリーの鞭を恐れているってのが大きいですな。あれを食らいたい奴はいないでしょうから」
オバは白いものがまじったヒゲを生えたあごをかいた。いつものクセだ。だが、いつもより口数が少ないような気がする。あたしがピートを自分より出世させたことに腹を立てているのだろうか?それまで忠実だった副々長が、下衆野郎にそそのかされて船長を殺した例は、実際にあるのだ。
「何か気になっていることがあるようだね」
ようやくオバはあたしの方を見た。
「資源と時間を浪費しているような気がするだけですよ。あそこには奴らがいるってのに」オバの口調は暗かった。彼が見つめる先には海があった。「あなたならランポートを世界で一番大きな町にすることもできるでしょう。だが、あそこに奴らがいる限り、そんなことをしたって何もなりはしない!」
「人魚たちのことを言ってるのかい?」
「そうです。クジラを獲って暮らしていたころ、奴らと偶然に出会ったことがあります。奴らはこの世のどんな女よりも美しい。しかし、血に飢えたサメと同じぐらい性悪なんだ!俺は知ってるんdねすよ。なにしろすべての仲間が殺され、生き残ったのは俺だけだったんですから」
「人魚のことも、この海域で暮らしている海賊のことも、忘れたわけじゃないよ、オバ。好機がめぐってきたら、まとめて面倒見てやるつもりさ。しばらくは奴らだって動けないだろう。だからこそあたしは、奴らの準備がととのう前にランポートを完成させたいのさ」
ずいぶん前のことだが、あたしはあのドライデンという若い水夫を会計係兼書記官にした。あまりにも奴が海賊に向いてなかったからだ。あたしのことを心底から恐れているのも好都合だった。あれならあたしを裏切るようなまねはしないだろう。
今日、深刻な顔をしたドライデンがあたしのところにやって来た。
「どうした?」
「三回も計算をやり直しました、船長。間違いありません」
「計算ってのは何のことだい?はっきり言いな!」
「資源が不足してます。今のペースで建設をつづけるのは無理です、船長。とりわけ黄金が足りません。木材や鉱石も。なにもかも少なすぎます!」
「それならヤナズレーに手紙を送って、もっと資源を送らせな」
「そうすることもできますが、船長はなにがあっても建設の手を休めちゃならないってご命令になりました。ヤナズレーから送ってもらうにせよ、今からじゃ間に合いません。その前に手持ちの黄金を使い果たしてしまいます」
あたしはドライデンの胸ぐらをつかみ、鼻っ面に一発お見舞いしようとしたが、すんでのところで思いとどまった。資源が足りなくなったのは別にドライデンのせいではない。あたしは胸ぐらをつかんでいた手を放し、襟元を直してやった。「黄金はなんとかする」
ドライデンは「どうやって?」と訊きたそうな顔をしていたが、これ以上の運試しはやめておこうと判断したようだ。
数分後、あたしは規則を破った部下を鞭でうっているピート・ガーリーを見つけた。
「そいつは何をしたんだい?」
「怠けたんですよ」
あたしはあえて追及しなかった。副長であるピートの仕事には、部下たちがだらけないようにすることも含まれているのだ。
かわりにあたしは言った。「アーノックに使いを出しな。まだ見つかっていない財宝を探すように言うんだよ。あたしたちには黄金が必要なんだ。とてつもなくね。近くに海賊がいるなら、埋められているお宝もきっとあるはずさ」
ピートの顔に戸惑いの色が浮かんだ。海賊の間には地中にある黄金には触れてはいけないという暗黙の掟があるのだ。くだらない掟だが、親父も含めて、多くの海賊がこの掟を破るぐらいなら飢え死にする方がマシだと考えている。だが、あたしは違う。あたしなら躊躇うことなく黄金をいただく。
「やるんだよ!」
「はい、船長」
門の前に散らばっていたのは、純然な恐怖に顔をゆがませた何十体もの石像だった。どんな彫刻家であれ、これほど生々しい表情を彫ることはできまい。これはメデューサの作品だ。警戒しながら君は門に近づいた。
メデューサを懐柔しようという試みは、ことごとく失敗に終わった。最近、彼女たちの指導者が海賊に捕らわれられたらしく、女王が帰ってきたときに受けるであろう罰を恐れるあまり、自分の判断では何もできなくなっているのだ。メデューサの魔女王キルカを味方につけない限り、この門は通れまい。
牢屋の中に捕らわれていたのは一人の女だった。だが、女の肌は薄緑色のウロコに覆われ、頭の上では髪のかわりに無数の黒い蛇がのたくっている。間違いようがない。この女はメデューサの魔女王キルカだ。
運の悪いことに、牢獄はミノタウロスとイフリートの一隊によって守られていた。彼らは命にかえても牢獄を守るつもりだ。
キルカの檻にかかっていた鍵を斧で壊し、あたしはメデューサの魔女を外に引っ張り出した。
「あんたは?」
傷だらけで、そのうえ疲れきっていたものの、あたしに問いかけられた蛇女は背筋を伸ばし、胸を張った。たいした気位の高さだ。だが、頭の小さな黒蛇たちがぐったりしていることからも、倒れる寸前であることがうかがえた。
「キルカじゃ」蛇女は言った。普通の歯の中にまじった長い二本の牙がことさら目立つ。キルカは堂々とした口調で付け加えた。「わらわはキルカ。女王である」
あたしは片手を差し出しながら言った。「あたしはダウニー・バルフォア。あんたを探していた」
「わらわを?なにゆえに?」
「その件はあとで。まずは休まないと。いまにも倒れそうじゃないか」
夜がふけていく。みんな寝静まり、起きているのはピート・ガーリーとあたしだけだ。
「俺にも船を預けてくれたっていいと思うんですがね」会話の途中、狙い済ましたタイミングでピートが言った。
あたしは聞こえなかったふりをした。
「いえね、<帰らずの海峡>で沈んでしまった船のことを考えてたんですよ。五隻ですよ!大損だ」
「言われなくてもわかってる!」あたしは声を荒げた。
「もっといい船長が乗ってれば、あれほどの大損害にはならなかったはずです」
「年季の入った連中ばかりだったさ」
あたしはピートに背を向け、歯を食いしばった。あの損害のことは思い出したくなかった。なのにピート・ガーリーめ、自分が指揮をとっていたら、ああはならなかったとぬかすのだ。あたしはピートを副長にしたことを後悔しはじめていた。副長になってからはこいつは変わった。
ピートが細かいところにこだわって皮肉な口をきくのはいつものことだが、二人っきりになると口が軽くなるようだ。そのせいで、黙るべきときを見誤ることがある。
「前に一度、親父さんがシーモンスターと戦うのを見たことがあります。俺ならもっとうまくやれたと思いますぜ」
ピートが反応するよりも速く、あたしの手は鞭のように素早く動いた。ピートは鋭くうめいてヨロヨロと後ずさり、あごに指を二本あてた。かつては傷ひとつなかったピートのきれいな顔に、三インチほどの深い傷ができ、血が流れ出していた。ピートの口がゆがみ、怒りのうめきがもれる。
ピートの顔を切り裂いたのは、親父からもらったあのナイフだ。あたしはナイフをピートの心臓につきつけた。
「次にそのお喋りな口を聞くときは、その傷のことを思い出すんだね!」
「俺が何をしたっていうんですか?」
「船長たちがヘマをして死んだのは、あいつらが間抜けで、あたしの親父に及ばなかったからだって言いたいんだろう?わたってるよ、ピート!あんた、あたしまで親父と比べるつもりじゃないだろうね?」
ピートの顔から怒りが消え、かわって自分が何を言ってしまったか理解した表情が浮かんだ。
「そんなつもりじゃ...」
「もういい!喉を切り裂かれなくて運が良かったと思うんだね!さあ、とっとと消えな!」
魔女王キルカが近づくと、その到着を待つことなくメデューサの塔の門が開け放たれ、何人ものメデューサがまろび出てきて女王をかきいだいた。
捕らわれ、幽閉され、救い出された顛末を話した後、キルカは家臣たちに自分は旅に出るつもりだと告げた。「わらわは運命の導きにしたがう」
<メデューサの門>をくぐり抜けてほどなく、大軍が追撃してくるという報告をたずさえて斥候が戻ってきた。君は立ち止まり、奇襲の準備をととのえ、敵が来るのを待った。だが、敵軍が視界に入るや否や、メデューサの情報キルカは妹たちの姿をみとめ、隠れていた場所から飛び出した。
「こんなところで何をしておるのじゃ?」キルカはきびしい口調で問いただした。
「あなた様は我らの長」一人が答えた。「長なき国に何の価値がありましょう?我らはあなた様と共に参ります!」
キルカは「呆れた」とでも言うかのように首をふった。
「この者たちはよく戦いましょう」キルカは君に言った。「無様な戦いぶりを見せたときは、この手で殺してやりまする!」
そんなわけで、君はメデューサたちが軍勢に加わることを許した。彼女たちの忠誠の対象が、君ではなくキルカであることは知っていたけれども。さいわい、少なくともキルカは君の指導力に心酔しているようだ。キルカを幻滅させない限り、メデューサたちは君の命令に従うだろう。
ランボートからの使者が到着するとすぐに、あたしはピート・ガーリーと”八本指”のオバ、それに書記官のトライデンを呼び集めた。全員がそろうのを待って、あたしはドライデンに手紙を渡した。
「読みな」
ドライデンは手紙を開き、目をとおした。その顔に、どうしたものかという戸惑いの色が浮かぶ。
「みんなに読んで聞かせてやりな!」
「え、いえ、あの」ドライデンは口ごもった。
ドライデンは咳払いし、手紙を読み始めた。手紙には、ランボートが完成したこと。鉄壁の守りを固め、造船所では<帰らずの海峡>での損失を穴埋めするために急ピッチで船の建造が進められていること。現在はヤナズリーから到着した船が海峡の警備にあたり、航行するすべての船に高額の通行料を取り立てていること。通行料を払わない船は没収処分にしていること、などが記されていた。
「これですべてです、船長」手紙を君に返しながらドライデンは言った。
「ここでの仕事は大体終わった。もう少しで帰れるよ」
「で、次はどうするんです?」
「人魚に戦いを挑むのさ、オバ。ちょっと仕返しをしてやりたいんだろう?」
オバはほほ笑み、うなずいた。
「よし」次にあたしはピート・ガーリーに向かって言った。「お前はランボートに戻り、あたしが戻るまで守備隊の指揮をとるんだ」
ピートの顔が曇った。あたしが厄介払いしたがっていることに気づいたのだろう。口論したのはまだ記憶に新しいところだ。
「はい、船長」
ピートがいなくなったら、オバを副長に任命しよう。そしてここでの仕事が片付いたら、ピート・ガーリーには死んでもらうのだ。近頃のピートはちょっと野心的すぎて、あたしの好みではない。
<<聖杯>>を町の中心部に運んでいくと、人々が驚いて集まってきた。このすばらしい品を納めるための混沌の眼を建てることを誰もが望んだが、最終的に決断するのは君であることは皆が認識している。この町を<<聖杯>>の恒久的な安置場所にするかね?
→勝利条件が「赤のプレイヤーを排除する」に変わる。
−−乙女の入り江−−
| 詳細 | |
| 勝利条件: | ピート・ガーリーを倒す |
| 敗北条件: | タウニー・バルフォアかキルカを失う |
| マップの難易度: | 「名人」ゲーム |
| 持ち越し: | タウリー・バルフォアとキルカ、および二人の呪文、技能、経験は、<<ジャイアントスレイヤー>>と一緒にすべて次のマップに引き継がれる自軍の勇者の最大レベルは 28。 |
ランボート周辺地域の最大の悩みは気が足りないことだ。船大工たちは最初の数週間ですべての木材を使い切ってしまった。造船所では、未完成のまま作業が中断してしまった六隻の船が、みじめな姿をさらしている。北から木材を運ばせるかわりに(それでは北方地域の木材が不足してしまう)、あたしは<乙女の入り江>を支配下に置くため、さらに南に進んだ。
<乙女の入り江>は船の建材としてうってつけの木が生い茂った広大な森に囲まれている。ランボートにも比較的近い。
もちろん抵抗があるだろうが、今回のあたしは艦隊を危険にさらすほど愚かではない。多数の船の出現は、人魚たちの注意を引いてしまうだろう、船は<猛き雌狐>のみ。密航船のように、一気に<乙女の入り江>に入り込み、戦闘はいっさい回避するつもりだった。結局、人魚とは何度か遭遇したし、シーモンスターを連れた人魚とも一度だけ出逢ったが、<猛き雌狐>を沈められることだけは避け、あたしたちは何とか<乙女の入り江>にたどりついた。
ぐずぐずしている暇はない。何人かを<猛き雌狐>の修理に残し、あたしはオバと残りの者たちを率いて探索のために上陸した。あたしが船を留守にしていたのは一日でしかなかったが、戻ってき来たとき、あたしは見張りをもっと残しておくべきだったことを悟った。いるべき場所に<猛き雌狐>がいなかったのだ!部下たちの姿は見えず、沈没した痕跡もない。まさしく「いなく」なってしまったのだ。
足首まで泥に埋まりながらのハイキングってのは楽じゃない。たとえ馬の背に乗りながらだとしてもだ。このあたりの湿地には獣道さえないのだから最悪だ。草木を切り開きながらでないと進めないのも肉体的な負担を重くしている。あたしは、剣や斧でつるや藪を切り払っている部下たちに交代で作業にあたるよう指示し、副々長のジム・ジャーニーを作業監督に任命した。奴にとってはとんだ災難だっただろう。
だが、こういった状況で自分がいかに頼りになるか見せようと、ジムは文字どおり部下たちの先頭に立って湿原を進んだ。ジムは他の者たちの数歩先を行き、道を作り、泥の深さを調べた。まさしく「探検家」といった風情だ。だが、ジムの注意はすべて地面に向けられていた。そのせいで、頭上から垂れ下がっていたつるを横に押しのけたジムは、罠を作動させてしまったことに気づかなかった。
長さが一m以上もある先をとがらせた丸太が近くの木の上から振り子のように落ちてきて、ジム・ジャーニーの胸を貫き、その命をあっけなく奪った。ジムにぶつかっても丸太の勢いは弱まらず、ジムの体をつきさしたまま、皆の目前で行ったり来たりを繰り返した。
あたしの隣にいたオバが言った。「罠があるということは、誰かが近くにいるはずです」
「ああ。それに、罠があるってことは、よそ者が好きじゃないみたいだね。これからは罠がないか、一歩一歩確かめながら進まないと」
「今度は俺が先頭に立ちましょう」そう言ってオバは馬から降りた。
あたしたちはジム・ジャーニーをその場に残し、前進を再開した。
腰をおろし、”八本指”のオバと避けを飲みながら、あたしは考えた。たぶん、何人もの部下がいる中で、あたしが信用しているのはオバだけだ。普通なら、「信用する」なんて時間の無駄づかいでしかない。心を許せば殺されるだけだ。だけどオバは違う。あたしにはこの老練な船乗りの欲しているものがわかるような気がした。オバは権力にも黄金にも興味がない。あたしの地位を奪うことにも無関心だ。そんな男がどうしてあたしを殺そうとするだろう?
オバは自分船を持ちたがっているようにさえ見えなかった。船長になりたそうなそぶりを一度でも見せたことがあったら、とっくの昔に船を与えていただろう。オバなら優れたリーダーになれるはずだ(そうでなかったら、オバを副長にしたりするものか)。だがオバは判断を下す立場になることを望んでいないようだ。
「なんでこんなことをしてるんだい、オバ?」我ながら唐突にあたしは尋ねた。
オバは白くなりつつあるあごヒゲをかいた。最近になってあたしは、このクセが出るのはオバが落ち着かない気分でいるときだと気づいた。
「こんなこと、と言いますと?」
「海賊さ。お前は、海の上にいられさえするなら、乗っているのはただの釣り船だってかまわないんじゃないのかい?」
オバは「まあ、そうです」というようにうなずいた。「日がな一日釣りをして暮らせたらいいでしょうなあ。実際、そうしようと思ったこともありますよ。とくに最近は、歳を食って動きがにぶくなってしまいましたから」
「何をとぼけたことを」そういってあたしはオバと自分のコップに酒を注ぎ足した。「乗組員の誰よりもお前はたくましくて、動きも素早いじゃないか!今、何歳なんだい?四十代?」
「もうすぐ五十になるんじゃなかったかと思いますよ。数をかぞえられないので、自信はありませんが」
だとすれば親父と同じぐらいということになるが、オバはもっと若く、健康そうに見える。
「で、なぜこんなことをしてるんだい?海賊なんてことをさ?」
二敗目を飲み干し、三杯目を注ぎながら、オバはじっと考え込んだ。あたしはオバが口を開くのを待った。相手が思慮深く考えているときは口を挟むべきではないというのも、オバから学んだことだ。
「船長が言ったとおりですよ。俺は海が好きなんです。ここが俺の居場所だし、どうせ死ぬなら海で死にたい」
「じゃあ、海賊をしているのは、勇士とかって呼ばれたいからなのかい?」
オバは首を横にふった。
「俺が海賊をしているのはね、海賊を殺せるからですよ」オバの言葉は氷の刃のようだった。
「海賊殺しを楽しんでるのかい?」あたしは躊躇いながら言った。こんな返答はまったく予想外だ。
「ええ。実に愉快だ。家族の仇ですからね!」吐き捨てるようにオバは言った。「クジラ漁を生業とする前の俺は、普通の漁師でした。そんなとき、海賊が村に襲いかかってきて、村人の大半を殺していきやがった!俺は数少ない生き残りの一人でした。その後、俺はブラカーダやエラシア、それにナイオンの海軍に加わり、あちこちに行きましたが、海賊とやり合う機会はあまりなかった」
「それで自分自身が海賊になったのかい?ずいぶん風変わりな選択をしたもんだね」
「そうですかね?ですが、海賊の一員になってみると、それまでよりずっと多く海賊を殺せましたよ。海賊は他の海賊を嫌っているってことが、誰にもまして俺にはよくわかりました。海賊は同業者がいることを好まない。だから、田野か遺族をみかけると襲いかかってくるんです。陸に上がるにしても、たいていは海賊たちの溜まり場になっている港に上陸するわけだから、酒場では揉め事がたえない。殺し合いになったり、酔っ払った相手を路地裏で待ち伏せて首をかき切るぐらいは日常茶飯事だ」
さらに一杯、オバは酒をあおった。目がすこしトロンとしてきていたが、顔には笑みが浮かんでいた。オバの目は落ち窪み、短い髪とひげには白いものが交じっている。浅黒い肌には小じわが目立った。
「殺された家族一人につき百人の海賊を殺してやりましたよ」オバは話しつづけた。「家族の仇をとり終わってからは、数えるのをやめました。それからも殺しつづけたのは俺自身のためです。俺から幸せを奪ったことへの復讐ですよ!」
オバと一緒に戦ったときのことを思い出したあたしは、罪のない連中が相手のときと海賊が相手のときでは、オバが別人のようだったことに思い当たった。海賊と戦うときのオバは狂人さながらで、一人で八人とか九人を殺すこともあった。これほどのことができるのはオバだけで、だからこそ親父もオバには一目置いていたのだ。オバが他の海賊一対一で戦うなら、自分は全財産をオバに賭けると、ブラック・バルフォアはいつも言っていた。多分、あたしもそうするだろう。
ところが、相手が商船の護衛や海兵だと、オバは滅多に命を奪わないのだ。
「家族は何人だったんだい?」この男の復讐心を満たすために血祭りにあげられた海賊の数を知りたくて、あたしは尋ねた。
「女房、赤ん坊、弟、親父、お袋...」
五人か。
一人につき百人を殺したというのだから、死んだ海賊の数は五百人ということになる!今、あたしが酒を酌み交わしている男は、復讐の神の化身のような奴だ。なぜ黄金や権力がこの男にとって意味をもたないか、あたしはようやく理解した。自分の船を持とうとしなかったのも無理はない。たった一人でそれだけの数の同業者を殺したのだ。海に生きるならず者なら、誰もがオバの首を狙うに違いない。だが、今のような表舞台に立たないようにしていれば、敵意はすべて本人ではなくオバを使っている船長に向けられる。親父は名うての海賊だったが、その評判作りにはオバが一役も二役も買っていたのではないだろうか?
あたしは乾杯するためにコップを持ち上げ、新しい副長にほほ笑みかけた。「負け知らずのお前に乾杯。お前の名簿にあたしの名前がないことを祈るよ」
あたしたちは同時に酒を飲み干した。
あたしはコップを置くと、オバもコップを置いて言った。「ご安心を。一緒に仕事をしている仲間を殺したことは、一度だってありませんよ」
「お前は自分の船なんて欲しくないんだろう?」
オバはほほ笑み、立ち上がった。「今のままで満足ですよ、船長。俺はあなたの副長っていう身分が気に入ってるんです」
それはそうだろう。なにしろ、あたしは海賊相手に戦いを繰り広げてきたのだ。復讐の機会には事欠かなかったことだろう。
今日は出だしこそ良かったものの、その後は下り坂を転がり落ちるがごとしだった。昨日、豚飼いたちと出逢ったおかげで、今朝は全員がたっぷりと豚肉を食うことができた。だが順調だったのは、とっておいた酒を少し飲んで口の中に残った脂を洗い流し、テントから出るまでだった。
両脇からオークの番兵二人に支えられながら、よろめく足取りで一人の男が野営地に入ってきた。オークたちはあたしに近づきたくないらしく、足を止め、男をぐいっと前に押した。
男の顔は泥と血でひどく汚れていたが、その顔には見覚えがあった。アーノックの船、<破壊神>の副長をしている男だ。ホルだかホブだか、たしかそんな名前だ。ボロボロの風体の男から強烈な悪臭がただよってきて、あたしは思わずあとずさった。
「ここで何をしている?」本来この男は、<破壊神>に乗り込んで<帰らずの海峡>の守備についていなければならないのだ。
「知らせを持ってもいりました、バルフォア船長」あたしの問いかけに男は答えた。「残念ながら悪い知らせです」
「どうやってここへ?<破壊神>で来たのかい?」
「いいえ、船長。歩きです。<破壊神>は敵の手におちました」
そう言って男は腰につけていた大きな袋の口をしばっていた紐をほどき始めた。
「どういう意味だ?敵って誰のことなんだい?」あたしは問い詰めた。
ようやく紐がほどけ、男は袋をひっくり返した。中身が泥の上にポチャっと落ちる。たちまちハエがたかってきた。最初それは青白い色をした玉のように見えた。男がかかとで玉をひっくり返す。そのときようやくあたしは、それが人の首であることに気づいた。見間違えようのない”禿頭”アーノックの顔があたしを見上げていた。
漂ってくる悪臭にかまわず、あたしは男の汚れたシャツをむんずとつかみ、息がかかるほどの距離まで引き寄せた。
「敵ってのは誰なんだい?」
「ピート・ガーリーです、船長」
あたしはピート・ガーリーにはランボートを、アーノックには艦隊を任せていた。力を分けることで、二人の野心を相殺しようという意図からだが、とんでもない間違いだったようだ。<帰らずの海峡>を警備していたアーノックに、ランボートへ帰還せよというあたしからの命令が届いたときの様子を、男(名前はホフだった)は聞かせてくれた。
「そんな命令は出してないよ!」あたしはホフの話をさえぎって叫んだ。
「俺たちはそのことを知らずに入港しました。出迎えに現れたピート・ガーリーにバルフォア船長がお待ちだからと言われ、俺たちは町の通りを歩いて一緒に城へむかいました。その途中、いきなり襲われたんです。襲いかかってきた奴らは、俺たちの三倍はいました。アーノック船長は三人ほど殺ったんですが、ピート・ガーリーのあの鞭に剣をからめ取られちまいまして。アーノック船長を自分自身の手で殺したガーリーは、部下たちに船長の首を切り落とすように命じました」
ホフは他の何人かと一緒に捕らわれたのだという。ピートはホフを選び出し、アーノックの首が入った袋を持たせ、他の奴らを縛り首にしたらしい。
「あいつは何か言ってたかい?」
「アーノック船長の首をあなたに届けろと言われました。それから、’これで俺も船を指揮する身分だ。それも、たった一隻じゃないぞ’とも言っていました。今やランボートとあそこに駐留していた艦隊は奴のものです。ヤナズレーも遠からず同じ運命をたどるでしょう」
「他には?」
「俺には何のことだかわからないことをいろいろと。’つけてくれた印のことは忘れねえぞ’とか何とか...」
自慢の顔を傷つけられたことを、ピート・ガーリーはずっと根にもっていたわけか。それならそれで好都合だ。怒ると男は馬鹿になる。だが、ちょっと顔を切られたぐらいでピートがあたしを裏切るとは思えない。もともとあいつは野心的な男だったのだ。発作的な行動ではあるまい。好機到来と見て、以前から考えていたことを実行に移しただけなのだろう。あたしを裏切ったことを責めるつもりはない。だが、あたしのものを奪ったとなると話は別だ。
「何か食べさせていただけませんか、船長?」
「安心しな」手にはすでにナイフが握られている。
「二度と腹がすかないようにしてやるよ」
ピート・ガーリーのスパイである可能性を考えて、あたしはホフを躊躇することなく始末した。命と引き換えにホフがガーリーと何らかの取引をした可能性は十分にある。ある晩ふと目がさめたら、枕もとにナイフを持ったホフが立っていないとも限らない。あたしは用心深い人間なのだ。
あたしは一部始終を見ていた”八本指”のオバをふり返った。「ピート・ガーリーは必ず殺す!わかったな?」
「はい、船長。機会があったら、その役目は俺が喜んで引き受けましょう」
あたしは誓った。全力をもってランボートを取り戻し、ピート・ガーリーの人形めいた首と胴体を離れ離れにしてやると。
君のメデューサの目は、徐々に闇に慣れていった。最初に気づいたのは、地面が銀の粉でもまいたようにキラキラと光っていることだった。次に君は、地面が動き、脈打っていることに気づいた。違う。地面ではない!それは互いにからみ合いながら這い回る、何百、何千匹という蛇の大群だった。
だが、君が前に進むと、蛇たちはまるで命じられたかのように左右にどき、通り道を作った。君が前進するのにあわせて、蛇たちが退路をふさいでいく。まるで一方の壁に君を導こうとしているかのようだ。
「そなたは我らと匂いが似ている」洞窟に軽く反響する声がした。「尻尾はどうした?」
声が聞こえてくる方を振り向くと、闇の中に一つの人影が見えた。メデューサだ。
君が質問に答えるよりも速く、メデューサが再び朽ちを開いた。「そなたの血は汚れておるな!」
「心は清らかじゃ!我はメデューサ。同族に使え、同族を導く者じゃ」
「汚らわしい奴め!」
「違う!わらわは女王キルカ!わらわを汚らわしいというそなたこそ何者じゃ?」見えぬ声の主にきびしく詰問した。
ここまで言われてようやく人影は前に進み出た。それはこれまで君が見たことのある誰よりも大きなメデューサだった。戦いになったらどれほどの力を発揮するか、想像もできないほだ!さらに、何十人ものメデューサが隠れていた場所から這い出し、君を取り囲んだ。
「ここの女王はわらわじゃ!」巨大なメデューサが言った。見れば魔女が使う護符や呪具を身につけている。
この邂逅の結末は「死」以外にありえないと悟り、君は先手を打って攻撃をしかけた。他のメデューサたちは、君の攻撃魔法から逃れようと後ずさりした。灼熱の炎。容赦なく敵を引き裂く稲妻。破壊をもたらす混沌の魔力が洞窟に吹き荒れた。蛇たちの焼き焦げる匂いがあたりに充満する。
ついにメデューサの女王は倒れ、両腕を天に向かって伸ばし、勝利を宣言した。
「我が名はキルカ!」すべての者に聞こえるよう、君は声をはりあげた。「我はメデューサ!我は女王なり!」
<乙女の入り江>に足を踏み入れたとき、こんな塔はなかった。珊瑚や青々とした海草が付着しているところを見ると、つい最近、人形たちが魔法を使って海中から浮上させたのだろう。恐るべき魔力の持ち主だ!
今すぐ奴らを攻撃するのは危険すぎるが、脅して追い払うことはできそうだ。<乙女の入り江>からの支援を受けられないとなれば、奴らといえどもこの塔を放棄するだろう。試してみるだけの価値はあるはずだ。
→自分たちでは君に太刀打ちできないと悟り、最後の人形が塔の頂上から黒い海面に身を投げた。これでようやく抵抗を受けることなく通行できるようになったわけだ。
「船長!船が三隻、まっすぐこちらに向かってきます!」見張り台に上っていた水夫が叫んだ。
あたしは急いで舳先に行き、持っていた望遠鏡を目に当てた。オバも望遠鏡を手にしてあたしの横に並んだ。
「あれはあたしの船だ!」
オバはあたしより少し冷静だった。「<破壊神>はいないようですな」
あたしは望遠鏡を降ろした。船べりに叩きつけて怒りを静めたかったが、きまぐれで壊すには高価すぎる。
「ピート・ガーリーがあたしを弱らせようと誰かをよこしたってことかい。面と向かい合う勇気はないってわけだ!」
「連中は戦闘準備をととのえています。喫水線が低い。空荷ですな。おそらく二隻は舳先が強化されている奴でしょう」オバは敵艦隊の観察をやめなかった。いい副長だ。もっと早くオバを出世させてやるのだった。
あたしは望遠鏡を目にあてなおした。「体当たりして、あわよくばそれでこっちを沈めちまうつもりだね。生きたまま海に放り出されたあたしを見つけたら、引っ張り上げて連れ帰れって命令をピートから受けてるに違いない。」
「捕虜を鞭で打ち据えるのがだ大好きな男ですからな」
「期待はずれに終わらせてやるさ。敵船はどれも喫水線が低すぎる。たしかに船倉はからっぽだね。でもそれは兵隊を満載してないって証明でもあるわけだ。あの船の船長たちは、捨て駒にされてることに気づいてるのかね?」
「そのことを教えてやりますか?金を握らせれば寝返るかも?」
ピート・ガーリーは何を考えている?あたしを殺せるか、それが無理でも<猛き雌狐>を沈めることは十分に可能だと思ったからこそ、この艦隊を差し向けたに違いない。ピートはあえて危険を犯すのが好きだが、愚か者ではない。これは検討を重ねた末の判断のはずだ。
「いや。こちらの準備がととのい次第、すぐに攻撃する。敵艦隊の船長は、あたしを嫌っていた奴らだけで構成されているに違いない。多分、あたしの命令で禁固刑や鞭打ち刑に処せられた奴らを集めたんだろうね。そんな連中に賄賂がきくもんか」
あたしは望遠鏡をベルトに挿し、まだ遠くにいる敵に向かってほほ笑んだ。敵艦隊の船長たちはあたしを憎んでいる。間違いない。連中は恨みを晴らしたがっている。あたしにとってはそこが狙い目だ。
「タウニー・バルフォア船長の名の下、この砦は俺たちが選挙している!」眼下の君に向かって水夫が叫んだ。
「お折れるのはバルフォア船長その人だけだ!」別の水夫が叫んだ。
門の近くを通ると、頭上の水夫たちが君の名を誇らしげに叫んだ。
「ピート・ガーリーの奴に、誰が<黄金海>の女王か、教えてやってください!」
君は水夫たちを振り仰ぎ、ほほ笑んでやった。
「”<黄金海>の女王”、か」
いい響きだ。きみはこの称号が気に入った。
朝日が昇る直前の時間帯にあたしたちは<破壊神>を見つけた。<破壊神>もこちらを見つけた。その日の大半をあたしたちはおいかけっこに費やした。最初はあたしがピートをおいかけ、次ぎはピートがあたしを追いかけた。だが、<猛き雌狐>と<破壊神>の速度と力は互角だ。結局、どちらも相手より優位に立つことはできなかった。
日がずいぶんと傾いてきた頃、あたしたちはようやく敵を飛び道具の射程圏内に捉えた。
「バリスタだ!」自分自身の手で舵輪を操りながらあたしは叫んだ。
甲板の指揮はオバに任せてある。オバは腕を高々と上げ、さっと振り下ろした。
三本の巨大な矢が<破壊神>に向けて放たれるが、むなしく海面に落ちる。<破壊神>が反撃してきた。バリスタの矢が一本、すさまじい音と共に<猛き雌狐>の船腹に突き刺さる。
「お前!」オバは水夫の一人を指さして言った。「下の被害状況を確かめてこい!」
あたしたちは何度かお互いに向けてバリスタを放ったが、最初の一発を除き、放たれた矢はことごとく的を外した。だが、あたしはそれでもかまわなかった。バリスタの撃ち合いでカタがついてしまっては期待はずれもいいところだ。あたしが望んでいるのは、船を横づけして<破壊神>に乗り込み、じかにピート・ガーリーと戦うことだ。
<破壊神>の舳先のあたりにピートの長い金髪がちらりと見えた。あそこだ!あそこへ行くのだ!
戦いの場でのあたしは、どんなときでも計算高い戦死だ。あたしが頼りにしているのはスピードと気転であって力ではない。だが、部下を率いて<破壊神>の甲板に飛び移ったあたしは、怒りが全身を駆け巡るのを感じた。あたしが求めているはピート・ガーリーの血、行く手を阻む者には己の愚かさを後悔させてやる。はじめてあたしは、ブラック・バルフォアに名声をもたらし、今でも海賊たちの間で語り草になっている凶暴な怒りに身を任せて戦った。
いったい何人の海賊を切り倒しただろう?気づくとあたしは舳先まで進んでいた。ピートが一段高くなった場所に陣取って戦っている。ピートのところに行く先には、まず階段を何段か上らねばならない。結果として何秒か不利な状況に置かれるという寸法だ。すでにあたしの部下が七人、折り重なるようにして甲板に倒れている。
あたしは周囲で繰り広げられている戦いを無視して階段の下に立った。
「俺とお前、けっこう楽しくやってたよなあ、タウニー?」口の端をゆがめるように笑いながらピートが言った。片手に愛用の鞭を持ち、もう一方の手に反身の剣を握っている。
「反吐が出る」あたしは言い返してやった。
ピートの鞭が稲妻のように走った。あたしは攻撃に備えて身構えていたが、それでもかわすことができなかった。あごの左側に鋭い痛みが走る。あたしはよろめき、一歩後ろに下がった頭の感覚がほとんどない。痛みは耐えがたいほどだった。下を見ると、白いブラウスに血がしたたっていた。
「おあいこのつもりかい?」今の一撃は、ピートのあごを走る真っ赤傷跡と同じような傷跡をあたしの顔に残すことだろう。
「俺の顔に傷をつけたことを後悔したが、このあばずれ女!」
「何だい?こんなことをしたのは、自慢の顔を台無しにされた腹いせだったのかい?それならピート、もう顔のことを心配する必要はないよ。いますぐ頭蓋骨からひっぺがしてやるからね!」
あたしは突進した。鞭が首にまきつき、息ができないほど締め上げるが、あえて無視する。剣を心臓に突き刺すまでの辛抱だ。あたしは階段を一気に上がりきり、剣をくり出した。だが、この一撃はピートの剣にはねのけられた。
サーベルを上にはらい、あたしは鞭を両断した。左手で首にからみついた鞭の先端をほどき、ずっと昔に親父からもらったナイフを抜く。
だが、ナイフを構えるよりも早く、ピートが前方に跳躍し、鞭の残っている部分を使ってあたしの手からナイフを叩き落とした。ナイフは甲板を転がり、階段の下に落ちてしまった。
「あいつを使ってゴリー・ゴーディーを始末するのを見てるからな」自信たっぷりの口調でピートが言った。「俺には通用しないぜ!」
ピートが鞭を投げ捨てた。お互い、武器は剣だけだ。ピートの剣さばきは巧みだった。敏捷さもあたしに負けていない。あたしたちは円を描くように動きながら間合いを計り、激しく切り結んだ。数分もそうしていると、あたしはにはピートがあたしを何らかの罠におびきよせようとしているのではないことが確信できた。ピートはあたしに正々堂々の勝負を挑んでいるのだ。だが、あたしの考えていることは違った。
足を滑らせ、あたしは店頭した。そのままゴロゴロと転がって逃げようとする。うつ伏せになったあたしは格好の獲物だ。だが、これはすべてあたしの演技だった。
ピートがあたしにとどめを刺そうとして近づいてきた瞬間、あたしは落ちていたピートの鞭を左手をつかんだ。鞭をピートの足にからませ、思いっきり引っ張る。ピートは思わず倒れた。慌てて立ち上がろうとするが、あたしの方が速い。ピートが逃げようとしたその瞬間、すでにあたしの剣はピートの顔を切り裂いていた。
絶叫し、空いている左手で傷ついた顔を押さえながら、ピートは船べりまで後ずさった。
「俺のか...」ピートは何か言おうとした。
だが、最後まで言う前に、あたしの剣がピートの命を断った。
−−振り返るな−−
| 詳細 | |
| 勝利条件: | ”わだつみの女王”とシーモンスターの孵化場をそれぞれ五日以内に攻め滅ぼせ |
| 敗北条件: | タウニー・バルフォアかキルカを失う |
| マップの難易度: | 「名人」ゲーム |
| 持ち越し: | |
深夜、扉が激しく叩かれ、あたしの眠りを妨げた。あたしはブラウスをひっかけ、ズボンをはき、扉を開けた。そこに立っていたのは”八本指”のオバだった。
「”わだつみの女王”と称する奴からメッセージが届きました」何の前置きもなく、オバは言った。
オバの口調と表情から、あたしにはそれがろくでもない知らせだとわかった。あたしは手を出し、オバが手紙を渡してくれるのを待った。だが、オバはくるりときびすを返して歩き出してしまった。どうやら「メッセージ」というのは手紙のたぐいではないらしい。
「待て。あたしも行く」
あたしは膝まであるブーツをはき、そこに親父からもらったナイフを挿した。ピート・ガーリーの敗北以来、ランボートはひっそりとしていた。地位の高い部下やあたしに盾突くだけの度胸がある奴は、ほとんど残っていない。ナイフだけあれば十分だ。それに、あたしのかたわらにはオバがいる。
埠頭であたしが目にしたのは、一隻の船だった。<蛇狩り>と名づけた新造船だ。ひび割れた船体やボロボロになった帆から判断すると、つい最近、戦いを経験したようだ。渡り板を歩いて甲板に降りると、妙に厚みのある黒い染みが一面をおおっていた。乾いた血だ!
「乗員は?」
オバは肩をすくめた。彼らがどうなったかは、神のみぞ知る、だ。オバはマストを指さした。
マストの表面には、文字が乱暴に彫られていた。
海は我らの物なり!−わたつみの女王’
「じつに簡潔明瞭じゃないか?」
「この船には百八十人が乗っていました。それがみんな消えちまった」
「<蛇狩り>の任務は何だったんだい
「南へ行き、<帰らずの海峡>の端がどうなっているのか調べることです
「いまいましい人魚どもめ」
<蛇狩り>の甲板から降りようとすると、何人かの水夫が起きてきて、大破した船を唖然とした顔で見ていた。
「沖まで曳航して、穴を開けて沈めてしまいな。もう誰もこの船には乗りたがらないだろう。まともに弔ってもらえなかった乗組員たちへのせめてもの手向けだ 」
オバはうなずいたが、すぐには動かなかった。あたしのことを実によくわかっている。命令が他にもあることを心得ているのだ。
「戦いを望んでいるのなら、望みどおりにしてやろうじゃないか。<猛き雌狐>と<破壊神>、それに<鮫の歯>の出港準備をととのえな。夜が明けたら出発するよ!」
ランボートを出航して一週間、あたしたちは海図に載っていない<帰らずの海峡>の南端海域に到達した。これまでにも、この海峡に足を踏み入れた、なおかつ無事に帰ってきた船は何隻か存在している。 だが、海峡を通り抜けた船となると皆無だ。おそらく<蛇狩り>が栄えある海峡突破第一号だ。しかし、人魚たちは予想以上に海峡をしっかりと掌握していたようだ。
船長室の扉がノックされたのは早朝のことだった。
「お入り!」
副々長の”汚れ顔”デリングが入ってきた。デリングは小柄だが筋骨たくましい三十がらみの男で、顔の左半分が茶色い痣におおわれていた。デリングを見ると、ついつい真新しいあごの傷に指をやってしまう。そして、あの下衆野郎、ピート・ガーリーのことを思い出してしまうのだ。
「船長、ちょいと気になってるんですが、人魚を殺すなってのは船長のご命令ですかい?」
「連中と船倉をしようってんだよ?なんであたしがそんな命令を出すのさ?」
「それがですね」デリングは落ち着かない様子で手をこすり合わせた。「昨夜、何人かが人魚を殺そうとしたところ、副長がとめたんですよ」
あたしは立ち上がった。なぜオバはそんなことを?
「デリング、正直にお言い。嘘をついたり、あたしに気に入られようとして大げさに話してるんじゃないだろうね?もしそうなら、腹を裂いて船べりから吊るし、カモメどもの餌にするよ!」
「とんでもねえ、船長。事の顛末はこうです。あれはオバの当直時間でした。俺はまだ起きていて、船倉でちょいと一勝負していやした。それにこれは全部、昨夜の当直たちから聞いた話なんですぜ」
デリングの説明によると、海中に人魚がいることに気づいた当直の水夫たちは、スパイだと思い、その人魚を追いかけた。普段は見つかるとすぐに潜って逃げてしまう人魚が、このときはいかなる理由かそうしなかった。どうやら負傷していたらしい。追いかけること数分、水夫の一人が銛を使って魚女を串刺しにしようとした、ところがオバはそれを制止し、それから間もなく追跡もやめてしまった。
オバは何を考えているのだ?オバのことをよく知らなければ、傷ついた人魚を哀れに思って命を助けてやったと考えたかもしれないが、あたしはこの数ヶ月の間にオバが人魚を何人も殺すのをこの目で見ている。オバが仏心をおこすなんて、これまでになかったことだ。
「よく知らせてくれた、デリング」あたしは言った。「だけど、”八本指”はお前の上役だ。これからも問題が生じたら、まずはオバの指示を仰ぐんだよ。人魚に関しては、あたしから別命がない限り、見つけ次第すぐに殺しな。わかったね?」
「かしこまりやした、船長!」
しばらくの間、あたしは座ったまま、オバの行動の意味をじっくり考えた。だが、どうしてもある一つの疑問には答えを出すことができなかった。どうしてオバは敵に対して甘くなったのだろう?
三人目の使者の生首が行く手で発見されるにおよび、あたしは軍議を開くことにした。あたしに呼ばれてオバと”汚れ顔”のデリング、書記官のドライデン、それからあたしの軍勢の主だったメンバー数人が集まってきた。
「考えが変わった。”わだつみの女王”を殺すだけじゃなくて、ついでに領土も奪ってやろうじゃないか!」
何人かが歓声を上げた。だが、オバだけは黙り込んだままだった。
「計画の変更は?」質問したのはオバだった。
「正直に言えば、このあたりの土地には手を出さないつもりでいた。すでに手を広げすぎているぐらいだからね。だけど、”わだつみの女王”は殺すだけじゃ不十分だ。精神的にだけでなく、物理的にも負かさない限り、人魚どもはまた襲いかかってくるに違いない。生き残った連中が海の底にひっそりと隠れ住むぐらいは許してやろうじゃないか。だけど、町や村、それに農場はあたしのものだ!他のものはすべてぶっ壊す!」
「そんあふうに破壊の限りをつくして、いったい何になるっていうんですか?」
「”わだつみの女王”は全世界に対する見せしめさ。将来、”わだつみの女王”みたいな支配者が現れても、”<黄金海>の女王”への手出しは躊躇するようにするためのね!」
再び歓声が上がった。あいもかわらず、こいつらは戦いに飢えているのだ。あたしはオバの黒い瞳を覗きこんだ。すくなくとも、オバ以外の奴らの準備はととのっている。
奇妙な目をした老人が切り株に腰かけている。まるで誰かを待っているかのようだ。
君の姿が視界に入ると、老人はピョンっと立ち上がり、ねれじた杖を掲げて大声をはりあげた。「生きるとは選ぶということ。汝に選択の機会を与えよう。左にあるは<神々の剣>。右にあるは<金剛石の盾>。攻撃と防御。いずれが汝にとっては大切か?この強力無比な神器を欲するなら、<ジャイアントスレイヤー>を置いてゆけ。ただし、手にできるのはいずれか一つ。さあ、汝の選択は?」
言い終わると老人はぱっと消えてしまった。このときになってようやく、なぜ老人の目に違和感を持ったかがわかった。老人の目には瞳がなかったのだ!
攻城戦の後、あたしは冷静さを保つように心がけ、略奪にはけっして加わらないことにしている。火を放って町全体を廃墟にしてしまうような愚か者がでないように見張っている者が必要なのだ。あたしが馬にまたがり、修羅場と化している町をながめていると、”汚れ顔”のデリングと数人の海賊が、オバに引きずられるようにして商人の家から出てきた。
激しい口論になり、頭に血が上ったオバたちは剣を抜いてにらみ合った。
「やめな!」両者はまさに戦い始めようとしていたが、叫びながらあたしが間に割って入ると、すぐに剣を下ろした。
「いったい何事だい?」
デリングはオバが自分に不当な仕打ちをしたと言いたげな顔をしていたが、唇をかんで言葉を飲み込んだ。揉め事の裁定を他人に任せる海賊はいないのだ。
あたしはデリングたちに向かって手をふった。
「あっちへお行き」そうデリングたちに命じてから、わたしはオバに向かって言った。「お前はあたしについておいで!」
あたしたちは誰にも話しを聞かれる心配のない町外れまで歩いていった。
「あいつらは町を燃やし尽くすつもりです!」
あたしはすぐに返答した。「そんなことはしないさ。やりすぎれば鞭でぶたれるってことは、全員が心得ているからね!」あたしはオバに近づき、背の高い副長と目線が同じ高さになるように、少しつま先立ちになった。
「そろそろ本当のことを話してくれないかい?実は”わだつみの女王”のために働いているんだろう?」
「誤解だ!」あたしの告発に驚いたような口ぶりでオバは叫んだ。
「人魚の恋人でもいるのかい?」
「違う。どうしてそんな馬鹿なことを訊くんです?」
「それはね、最近のお前は敵と戦ってる姿より仲間と争ってる姿の方が目につくからさ!寝返ったんじゃないのかい?」
オバは首を横にふり、背筋を伸ばした。あたしはオバに見下ろされるような格好になった。
「証拠もなく俺の忠誠心を疑うなんて!」
「それなら言ってほしい。どうして人魚を見逃してやったんだい?仲間と殺し合いを始めかけたのはどうしてだい?」あたしは少しだけ口調を和らげて尋ねた。
この質問はオバの意表をついたようだ。オバは数歩下がり、短いヒゲが生えたあごをかいた。オバはあたしに背を向け、言った。
「これ以上、あの連中、つまり人魚を殺したくないんだ。あいつらは俺にとって敵じゃない」
「あいつらはあたしの敵だよ!つまりお前の敵でもあるんだ!」
オバは再び体の向きを変え、正面からあたしを見据えた。今度はオバが怒りで赤くなっている。
「敵と言うが、あんたに味方はいるのか?いつまでこんあことをつづけるつもりなんだ、タウニー?戦って、戦って...俺は自分の復讐心が癒されることはないだろうと思っていた。だが、征服と殺戮をひたすら繰り返すあんたに比べたらかわいいもんだ。あんたときたら、終わりってものがない!」
あたしは口をへの字に曲げたまま黙ってオバの叱責が終わるのを待ち、それからおもむろに口を開いた。「あたしは自分のものを取り返してるだけさ」
「そんなのただの口実だ!敵がいなくなると、あんたは戦う相手ほしさに、ピート・ガーリーが歯向かうようにしむけた。ピートはただ船をほしがっていただけだったのに。ピートより格下のやつらに何十隻も船を与えておいて、ピートにはおあずけを食らわせるなんて!ピートがあんなことをしたのはあんた自身のせいだ。そのためにアーノックみたいないい奴が殺されるはめになっちまったんだ!」
あたしは親父からもらったナイフを抜き、オバの首に突きつけた。
「おしゃべりがすぎるよ、副長!」
オバは口を閉じたが、目に宿った怒りの色は消えなかった。ナイフを突きつけられていなかったら、オバは喋りつづけていただろう。
「あたしが何を考えてるか、お前ならわかるはずじゃないか!」
「ああ、わかるとも!あんたがどんあ風に変わったかもな。俺にも経験があるし、その結果はごらんのとおりだ。ひとりぼっちになり、疲れ果て、傷つくんだよ!」
そう言ってオバは左手を持ち上げた。指は三本しかない。小指と薬指があった場所はもはや肉の突起にすぎず、釣り針にかけられた生餌のようにビクビクとけいれんするばかりだ。ゆっくりとオバがあたしに向かって手をのばしてきた。振り払おうと思えば振り払えるぐらいの速さだ。だが、あたしはそうしなかった。オバの手があごの横についた傷にふれる。
「職務を果しな、オバ」あたしはしっかりした口調で言った。「さもないと、他の誰かを副長にしなければならなくなる」
あたしはオバの首すじに突きつけていたナイフを引っ込め、急いでその場を去ろうとした。だが、オバは言いたいことをすべて言い終わったわけではなかった。
「タウニー、少なくとも俺の殺しには理由がある」あたしは立ち止まったが、振り返りはしなかった。
「俺は家族の仇が討ちたかった。あなたはなぜ殺すんだ?」
昨夜、<錆びたジョッキ>亭の夢を見た。
ずいぶん長いこと、あたしは自分が育った酒場のことをすっかり忘れていた。それなのに、今ごろどうして夢に見たりしたのだろう?それに、あの夢はずいぶんと真に迫っていた...
あたしは七つか八つだった。髪をおさげにしていて、頬には泥がついている。着ているのは、あたしが自分を踏んづけて転ばないようにとお袋が丈を詰めてくれた、裾が広がった古いスモックだ。このスモックしか着るものがなかったあたしは、冬になると寒くてどうしようもなかった。だからあたしは冬が大嫌いだった。
あたしは酒場の喧噪の中をちょこちょこと動き回っていた。どうやら何隻かの船が入港して、船員たちがどっと上陸してきたようだ。店内は身動きできないほど混んでいて、あたしは汗臭い酔っ払いたちの間をぬうようにしなければ進めなかった。一人の酔っ払いがあたしのおさげをつかんだ。後ろの引っ張られ、あたしは危うく転びそうになった。ものすごく痛かったけど、あたしは泣かなかった。涙はこのろくでなしどもの嘲笑をさそうだけだからだ。
水夫がまたあたしの髪を引っ張った。今度こそあたしは転んだ。そんなあたしを見て、水夫の仲間たちは笑い転げた。後で酒に唾を混ぜてやろうと思って、あたしはそいつらの顔を目に焼き付けた。
立ち上がったあたしは、店の奥にある席に向かった。その席には四人の男が座っていた。あたしは運んできた二つのパンを男たちの前に置き、目を合わせないようにしながらすぐに立ち去ろうとした。
暴漢に気づいたのはあたしだけだったようだ。長いナイフを持った三人の男が、こちらを目指して突進してきた。あたしは凍りついた。逃げ場はない。あたしは床に倒され、二回ほど踏みつけられた。頭上ではナイフと拳の応酬が繰り広げられている。あたしは悲鳴を上げ、大声でお袋に助けを求めた。だがお袋は、酒場の亭主が近づく者すべてに手斧を振り回しているカウンターの背後に逃げ込んでしまっていた。
あたしはひとりぼっちだった。打ち身になったところが痛かった。怖かった。左右には二つの死体が転がっていた。だれかがおさげをつかんであたしを持ち上げた。あたしは叫んだ。邪魔だからあたしを殺そうというのだろうか?それとも、安全な場所まで連れて行ってくれるのだろうか?
どちらでもなかった!あたしをつかみ上げたのは、席に座っていた男たちの最後の生き残りだった。男は鋭い切っ先をあたしの腹に押しつけた。
「下がれ!下がるんだ!」男はいきなり襲いかかってきた暴漢たちに向かって叫んだ。
あたしを捕まえている男と扉の間には、二人の暴漢がいた。なぜかあたしには、男が外に出たがっていることがわかった。
「そんなガキを人質にしたからって、俺たちが手前をバラすのを躊躇うと思ってるのか?」
あたしはお袋を見て、何とかしてと目で訴えかけた。だが、お袋は勝手口から貯蔵庫に逃げ込んでしまった。あたしの目からは涙がこぼれた。
「見逃してくれ!」あたしを捕まえている男が言った。「欲しいなら地図はくれてやるから」
どうやらお宝か何かがこの争いの原因らしい。自分がどうして死ぬはめになったのかわかっただけでも良かった。
「手前を生かしておいたら」暴漢の一人が応えた。「誰かれかまわず黄金のことを言いふらすに違いねえ。駄目だな。手前はここで死ぬんだ!」
あたしもろともこの男を殺し、隠された財宝を手に入れるつもりでいることは、暴漢たちの目を見るだけでわかった。それが年端も行かない子供であろうと、障害になる者は許さないというのだから、見上げた心意気だ。
男の力はものすごかった。だけど、あたしは必死に身をよじり、渾身の力をこめて男の腕に噛みついた。腹のあたりに激痛が走った。もっとも、後で見ると、それはほんのかすり傷でしかなかった。床に落ちた瞬間、あたしはテーブルの下に転がり込んだ。同時に暴漢たちが男に襲いかかる。男にとどめを刺すと、二人の暴漢は素早く死体の懐をさぐり、しわくちゃになった羊皮紙を取り出した。
あたしを捕まえていた男と言葉を交わした方の暴漢が、あたしに頭を向けてウィンクした。
「助かったぜ。帰りにここに寄ることがあったら、お嬢ちゃんに何か買ってやるからな」
だが、男は二度と<錆びたジョッキ>亭に姿を現さず、あたしはその晩、床にぶちまけられた血を嫌というほど拭かなければならなかった。
夜更け。起きているのは夜警ぐらいのものだ。あたしは誰もが寝静まっているものだと思っていた。ところが、オバまだ酒瓶を手に、消えかけた火の前に座っていた。中身を飲み干すまでは寝ないつもりらしい。口論して以来、あたしたちの関係はぎくしゃくしていた。少なくとも”汚れ顔”のデリングは、この軋轢に気づいている。何かにつけてあたしの味方をしようとするからだ。大方、自分の船が欲しいとかっていうたぐいの下心があるのだろう。
そういった分不相応な野心は、適当な頃合を見計らってつぶしておかないと。
あたしは火を挟んでオバの正面に座り、酒瓶をよこせというように手をのばした。しぶしぶオバが酒瓶をわたす。ぐうっと飲んでから、あたしは酒瓶をオバに返した。
「家族の仇なら、もう何回分もとっただろう、オバ」あたしは途中で終わっていた話題をもちだした。「なのにんなぜ殺しつづけるんだ?」
一瞬の躊躇いもないオバは答えた。「最近、同じ質問を自分自身にぶつけてみましたよ。ずっと昔に仇討ちは終わってるってのに、どうして殺すのをやめられないのかってね」
あたしたちはさらに何口か酒を飲み、勇気を奮い起こし、再び口を開いた。
「お前は幸運な男だよ。以前は殺し以外のことも知ってたんだから。それにひきかえ、あたしときたら、殺し以外のことは何ひとつ知りやしない。泳ぎ続けないと死んじまうサメみたいなもんさ」
なぜオバにこんな話をしているのだろう?あたしは酒のせいだと自分の言いきかせようとした。
「殺すのをやめない限り、他のことはいつまでたってもわからんでしょうな」
「そいつは無理だ。振り返るわけにはいかないのと同じことさ。振り返ったって、見えるのはろくでもないものばかりだしね」
オバは心得顔でうなずいた。
「親父さんのことですか?お袋さんのことですか?それとも<錆びたジョッキ>亭のことですか?」
どうしてあたしの考えていることがわかったのだろう?まるであたしの夢に入り込んでいたようだ。
「お前に<錆びたジョッキ>亭の話をしたことはなかったはずだけど?」
ため息をつきながらオバは言った。「俺は親父さんの船にずいぶんと長く乗ってたんですぜ、タウニー」
あたしは一瞬でしらふに戻った。体がふるえだす。あたしはオバに「どういう意味だ」と尋ねたかったが、答えを聞くのが怖かった。”<黄金海>の女王”にして世界中で最も恐れられている海賊であるあたしが「怖い」だなんて!
それから一週間、あたしは必死で昔のことを思い出そうとした。そうやって思い出した中に、今まですっかり忘れていた記憶があった。それは”八本指”のオバに関する記憶だった。あたしの記憶の中のオバは、今よりずっと若々しく、指もすべてそろっていた。
身長も今より高かった気がする。暑い夏の日、上半身裸のオバがブラック・バルフォア船長の供をして町にやって来た。オバが用心棒であることは、誰の目にも明らかだった。一対一でオバに勝負を挑むのは愚か者だし、三人がかりでも無謀のそしりはまぬがれないだろう。ブラック・バルフォアがオバをそばに置いていたのも当然だ。
このオバの姿を今まで忘れていたのはどうしてだろう?
あたしが初めて親父を見たときも、オバはかたわらにいた。あたしは十歳で、羽振りのいい海賊(親父のことだ)にすっかり夢中だったから、用心棒なんて目に入らなかったのだろう。親父がかぶっていたつば広の黒い帽子のようなもので、当時のオバは親父のアクセサリーでしかなかった。
あの晩のあたしは忙しかった。それでもあたしはブラック・バルフォアとその一団にちらちらと目を向けずにはいられなかった。お袋が同じ席に座ってからはいっそう気になった。お袋とバルフォアは長いこと話こんでいた。その夜遅く、店の隅でお袋とオバが声をひそめて言い争っていた。お袋は巨漢のオバをあろうことか平手打ちした。あのとき、オバがどうして殴り返さないのか、あたしには不思議だった。お袋を殴り返すかわりに、オバはじっとあたしを見つめた。あたしは顔をそむけた。盗み見ていたと思われるのが怖かったのだ。
翌朝、重い足取りで階段を降りてきたブラック・バルフォアは、店の中を掃除しているあたしを見て、今も持ち続けているあのナイフをくれた。そして、ナイフの使い方を説明し、不意打ちこそ採鉱の戦法なのだから普段は隠しておけと教えてくれたのだ。あの言葉があたしの人生を変えた。認めるのも腹立たしいが、あたしはお袋よりも親父が好きだった。それはすべてこの一見があったからだ。
そしてさらに、別の記憶が剣のようにあたしの心を切り裂いた。それは今まで一度も思い出したことのない記憶だった。
親父からナイフをもらった直後、オバが親父を探して階段を降りてきた。横を通り過ぎるとき、オバはあたしをしげしげと見た。それがどういう意味を持つまなざしだったのかはわからなかったが、どうしてこの大男は太ももに空の鞘をくくりつけているんだろうと思ったものだ。
賭けに負けて、ナイフを巻き上げられてしまったのだろうか?それとも勘定を支払うのに、現金の代わりにしてしまったのだろうか?
それとも、船長に託したのだろうか?小さな女の子に与えるため。
まったく、不意打ちってのはたしかに最高の戦法だ。
今朝、”わだつみの女王”との戦いの方針について話があるふりをして、あたしは誰にも盗み聞きされる心配がない場所にオバを連れ出した。
「<錆びたジョッキ>亭でのあの晩、お前とお袋は何を話していたんだい?」
オバは目を見開き、息を飲み込んだ。その様子はまるでいきなり喋れなくなったように見えた。オバの目が左に動いた。嘘をつくつもりだ。あたしは直感した。
「お前は親父と一緒だった」オバが何か言うより先に、あたしが口を開いた。「お袋はお前たちと同じ席に、ずいぶん長いこと座っていた。お前たちのところにパンを運んだのをおぼえてるよ。他の奴らはへべれけになるほど飲んでたのに、お前はただの一杯さえ飲まなかったね。あの頃のお前はヒゲを生やしていなかったし、指も全部あった。親父が気晴らしに外に出ると、お前とお袋は店の奥にひっこみ、何事か言い争いを始めた。しばらくして、於福がおまえをひっぱたいた」
オバはまだ何も言わない。「思い出したかい?」
「ええ、思い出しましたよ」
「で、何を言い争ってたんだい?」
「訊かないでください。今はまだ、話すべきじゃないこともあるんだ!」
「あたしに逆らおうってのかい!」あたしは声を荒げた。「お言い!ただし、嘘をついたりしたら、この場で八つ裂きにしてやるからね!」
オバは押し黙った。よほど言いたくないらしい。しばらくして、ようやくオバは口を開いた。「お袋さんはブラック船長に、あの子はあたなの子供だって言ってましたが、俺はそんなことありえないって知ってたんです」
「なぜ?」
「あの晩、ブラック船長は階段を上がってる途中で完全に酔いつぶれちまいましてね。お袋さんの部屋には行ってないんですよ」
ナイフと空っぽの鞘。お袋との口論。殺戮に喜びを覚えなくなった後もあたしと一緒にいてくれたこと。すべてのことがある一つの事実を暗示していた。
「お袋は嘘をついてたのかい?」
「ええ。俺に向かってお袋さんは、あなたには何も言わないでくれって言ったんですよ。あの頃の俺は、どこにでもいる海賊でしかなかった。だけどブラック船長は貴族も顔負けの大金持ちだ。お袋さんはブラック船長に、あなたの養育費をたまに送ってほしいってせがんでました。もし俺のせいで養育費の話が駄目になったら、あなたを寒空の下に放り出して死なせることになってしまうって言われましてね」
あたしはオバに背を向けた。目が熱い。あたしはあふれ出ようとするものを押しとどめられなかった。他人の前で涙を流したのは何年ぶりだろう?
「ブラック船長はお袋さんに一度だけ金を送ったけど、すぐに養育費のことなんか忘れちまいました。かわりに俺ができる限りの金を送りはじめたんです。お袋さんは船長からの送金だって思ってたでしょうね」
「へえ、そうかい。あたしは一銭も受け取っちゃいないけどね。おおかた、金はみんなお袋と酒場の亭主の懐に入っちまったんだろうね」
オバに泣くところを見られるのは嫌だった。あたしは誰にも見られない場所を求めてその場から逃げ出した。
走り去るあたしの背後でオバがつぶやくように言った。「すまなかった」
気持ちはあたしも同じだった。
”わだつみの女王”の宮殿を守る防壁は崩れた。だが、人魚どもは素早く海底に逃げ込んでしまい、奴らの細い首を絞めてやることはできなかった。戦いはまだ終わっていないが、敵を蹴散らすことには成功した。今日のあたしは何だか凶暴な気分だ。
捕虜の一人から”わだつみの女王”が逃げ込んだ先を聞き出すのに、たいした手間はかからなかった。東には女王がよく滞在している入り江があるらしい。女王はそこに逃げ込んだはずだとのことだ。
勝つには勝ったが、残念ながら思い描いていたような致命傷を敵に与えることはできなかった。こうしている間にも、”わだつみの女王”の入り江には、人魚の軍勢が終結しつつあるに違いない。西の秘密の孵化場では、今まで以上の数のシーモンスターが育てられている。先に孵化場を破壊すれば、”わだつみの女王”はあたしには手出しできない海底に逃げ込み、将来、こちらがまったく予想していないときに攻撃をしかけてくるだろう。だからといって女王を殺すことを優先すれば、シーモンスターが増えてしまい、まったく勝ち目がなくなってしまう。
いずれにしてもあたしの負けだ。勝つためには両方を同時に攻撃するしかない。もちろん、この離れ業を成功させるのは容易なことではないだろう。
船着場に行こうとする君を、暗い雰囲気の女性が呼び止めた。
「お知らせしたいことがございます」
「情報料は?」
「いりません。人魚がいなくなれば、それで満足です」
「なるほど。で、知らせたいことというのは?」
「人魚たちはこの辺りの海域を厳重に監視しています。シーモンスターたちの孵化場を破壊するつもりでしたら、この港を出航してから五日以内にやりとげないと。これを過ぎると、”わだつみの女王”のしるところとなります。知られたら最後、”わだつみの女王”は海底に戻り、勝ち目がないほどの大軍団を引き連れて戻って来ることでしょう」
「協力に感謝する」
秘密の孵化場を五日以内に見つけ出すのは容易なことではない。自分自身が出発する前に、他の船を出航させ、”わだつみの女王”を探させた方がよさそうだ。
「海賊女王に栄光を!」歓声を上げながら海賊たちは鎖をほどいた。
「”わだつみの女王”に目にもの見せてやってください!」海賊たちは口々に叫んだ。「だけど、急がねえと。人魚たちは俺たちのことをいつだって見張ってます。五日もすれば、シーモンスターの孵化場にいる連中は、姉御がここを通ったことを知って、海底に逃げ込んでしまうでしょう」
昨夜遅く、あたしはオバを残して<猛き雌狐>の甲板からすべての乗組員を追い払った。風があたしの長い髪をなぶる。あたしは上陸挺の一つを指さした。
「二週間は生きられるだけの食料と水が積んである」
「どういうことだ?俺が何かヘマをしたか?」
オバの目をまっすぐに見ることができなかったあたしは、船べりに近づき、暗い夜空にまたたく星々を見上げた。
「家族の仇討ちは終わりだよ、オバ。おまえ自身、仇討ちは終わったって思ってるはずさ。だから殺しの本能をなくしちまったんだ。このままだとお前、死ぬよ」
「俺は船を降りないぞ!」
「いいや、降りるんだ。引退するんだよ、オバ。気持ちのいい静かな場所を見つけな。そこに家を建てて、魚を釣って暮らすんだ。船を買ったっていい。元手になるだけの金も積んである。とにかく、海賊以外のことを始めるんだ。これ以上、海賊をつづけるのは、お前には無理だよ」
オバのごつい手があたしの肩をつかんだ。振り払おうとしたが、できなかった。なぜなら、肩をオバにつかまれているのは、あたしにとって心地よいことだったからだ。
「タウニー、あの頃の俺は若く、憎しみではちきれそうだった。今の俺は、お前と二度と離れ離れになりたくない」
あたしはオバの手を肩からどかし、両手で包み込んだ。
「あんたはあたしの父親かもしれない。だけど、ブラック・バルフォアもあたしの父親なんだ。わかるだろ、オバ?あたしはブラック・バルフォアの世界で生きるように鍛えられてきたんだよ」
「わかるもんか!なぜ俺と一緒に来るわけにはいかないんだ?」
「あたしたちは正反対だからさ、オバ。あんたの心にはいつでも過去のことが、家族が殺された日のことがある。だけどあたしは...過去を振り返るわけにはいかないんだ!そう、けっして!」
オバに気持ちを理解してもらえたかどうかはわからない。だが、船を降りるようにあたしを説得するのが不可能だということだけは理解してくれた。力を合わせてあたしたちは上陸挺を暗い海面に下ろした。いきなり、オバがあたしを抱きしめた。オバは大きな腕をあたしの背中に回し、一分近くその格好のままでいた。あたしは黙ってなすがままになっていた。オバの温もりがあたしを包み込む。あたしはオバの匂いを一生忘れないだろう。
それからあたしの本当の父親は縄ばしごを降りて上陸挺に乗り移り、オールを漕いで闇の中に消えていった。
おそらく二度と会うことはないだろう。そう思いつつ、あたしはオバを見送った。
「じゃあね」親父のナイフの柄を指でなでながら、あたしは言った。
オバのナイフ。あたしが人生の大半を一緒に過ごしてきたナイフだ。
<猛き雌狐>の甲板に立ち、あたしは”わだつみの女王”の玉座が波間に没していく様子を見守った。周囲には大勢の人魚が死んでプカプカと浮かんでいる。どこを見ても、目に入ってくるのは死と、炎と、破壊だけだ。
新しい副官に任命した”汚れ顔”のデリングがあたしの傍らに寄ってきた。
「オバにこんなものを見せずにすんでホッとしてるよ」何を言ってるか自分でもよくわからないままあたしは言った。
「そうですな」デリングが応じた。「俺はあの腰抜けが昔っから気に食わなかったんですよ!まったく、あんな奴がどうして男の中の男なんて言われてたのやら!あいつときたら、いつだって女々しいことばかり言いやがって...」
親父からもらったナイフが、無礼な船乗りの言葉と命を断ち切った。あたしは手についた血を見つめ、副長だった男の死体に目を移し、壊滅した”わだつみの女王”の軍勢に視線を戻した。もしオバがこの場に居合わせたら、実際にはまったくの赤の他人であるにせよ、あたしは確かにブラック・バルフォアの娘だと納得したに違いない。
人魚たちは海底に逃げ込んだ。馬鹿でない限り、しばらくは戻ってこないだろう。あたしにとって大変なのはこれからだ。征服した土地をすべて掌握しなければならないのだから。
あたしは共に船出した連中のことを思い浮かべてみた。”禿頭”アーノック、ピート・ガーリー、”斧使い”フォズ、書記官のドライデン...そして”八本指”のオバ。今も生きている奴はほとんどいない。同じ船に乗っているのは、もはやドライデンだけだ。
だが、過去を振り返るのはこれぐらいで十分だ!終わったことを考えたからといって、それが何になるというのだ?
今は明日の、そして将来のことを考えるべきときだ。あたしは愛する海を見つめた。西の水平線に日が沈んでいく。笑みがあたしの顔に浮かぶ。
「次は何だろうね?」誰にともなくあたしは問いかけた。
−−ラストナレーション−−
後にあたしは、”八本指”のオバ、つまりあたしの本当の親父が、<黄金海>の島の一つに腰をおちつけたことを知った。オバは釣り舟を買い、海岸の近くに家を建て、残りの人生をそこで過ごすつもりらしい。ただ、近くに住んでいる未亡人と親しげにしていたという証言もある。ふむ。まあ、幸せそうで何よりだ!